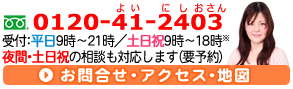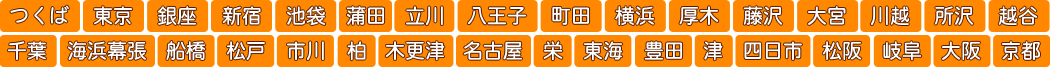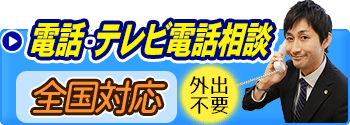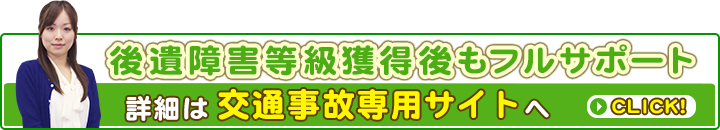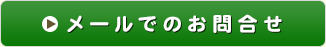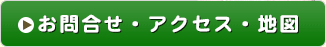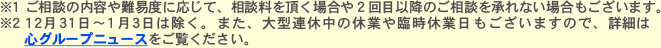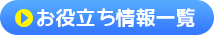脊柱の変形障害
症状例:首の手術をした
脊柱の後遺障害は,次の表のとおり,6級5号から11級7号までの等級が認められます。
| 6級5号 | 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの |
|---|---|
| 8級2号 | 脊柱に運動障害を残すもの(脊柱に中程度の変形を残すもの) |
| 11級7号 | 脊柱に奇形を残すもの |
脊柱の変形障害には,「脊柱に著しい変形を残すもの」,「脊柱に中程度の変形を残すもの」,「脊柱に変形を残すもの」の3つがあります。
脊柱に著しい変形を残すもの
「脊柱に著しい変形を残すもの」には,エックス線写真,CT画像,MRI画像(以下「エックス線写真等」といいます。)により,脊椎圧迫骨折等を確認できる場合であって,次に当たるものをいいます。
- 脊椎圧迫骨折等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し,後彎が生じているもの
- 脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し,後彎が生ずるとともに,コブ法による側彎度が50度以上となっているもの
「前方椎体高が減少した」とは,減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が,減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%以上であるものをいいます。
脊柱に中程度の変形を残すもの
「脊柱に中程度の変形を残すもの」には,エックス線写真等により脊椎圧迫骨折等を確認することができる場合であって,次に当たるものをいいます。
- 2個以上の椎体の前方椎体高が減少し,後彎が生じているもの
- コブ法による側彎度が50度以上あるもの
- 環椎又は軸椎の変形・固定により,次のいずれかに該当するもの
- (1)60度以上の回旋位となっているもの
- (2)50度以上の屈曲位又は60度以上の伸展位となっているもの
- (3)側屈位となっており,エックス線写真等により,矯正位の頭蓋底分の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上の斜位となっていることが確認できるもの
脊柱に変形を残すもの
「脊柱に変形を残すもの」には,次のものが当たります。
- 脊椎圧迫骨折等を残しており,そのことがエックス線写真等により確認できるもの
- 脊椎固定術が行われたもの
- 3個以上の脊椎について,椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもの
脊柱の変形障害における労働能力喪失率
1 脊柱とは?

脊柱とは、頚椎、胸椎、腰椎、仙骨、尾骨が連なって構成された、体幹の中軸をなす骨格のことをいいます。
脊柱には、以下の機能が備わっています。
①脊髄をはじめとする神経組織を保護する機能
②躯幹を支持する機能(以下「支持機能」といいます)
③体幹の運動に関する機能(以下「運動機能」といいます)
2 変形障害に関する後遺障害等級
脊柱の変形障害に関する後遺障害等級、及び、労働能力喪失率表記載の労働能力喪失率は下表のとおりです。
| 後遺障害等級 | 後遺障害の内容 | 労働能力喪失率表の数値 |
|---|---|---|
| 6級5号 | 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの | 67/100 |
| 8級2号 | 脊柱に運動障害を残すもの | 45/100 |
| 11級7号 | 脊柱に変形を残すもの | 20/100 |
3 脊柱の変形障害に関する労働能力喪失率の考え方
⑴ 脊柱の変形障害がある場合の労働能力喪失率については、加害者側より、労働能力喪失率表の数値よりも小さな喪失率にすべきであるとか、労働能力の喪失はそもそも存在しないといった主張がなされることがあります(特に変形の程度が小さい場合はこの傾向が強いです。)。
⑵ 裁判例においても、労働能力喪失率表の数値から単純に労働能力喪失率を認定するのではなく、変形障害の内容や程度、支持機能・運動機能に生じている支障の内容や程度、被害者の職業・減収の程度・業務上の支障の内容や程度、疼痛や神経症状の有無、被害者の年齢等の様々な要素を総合的に考慮した上で、個別具体的に労働能力喪失率が判断されています。
個別具体的な判断の結果、労働能力喪失率表記載の数値よりも低い労働能力喪失率を認定した裁判例や、労働能力喪失期間を分けた上で労働能力喪失率を逓減させた裁判例(例えば、症状固定時から10年間は20%、その後10年間は10%、その後10年間は5%というような方式です。)も少なくありません。
以上のとおり、適切な労働能力喪失率を獲得しようとすると、労働能力の喪失に関する個別具体的な主張・立証が必要不可欠となりますので、脊柱の変形障害についてお困りの方交通事故の後遺障害に詳しい弁護士に相談することをおすすめいたします。