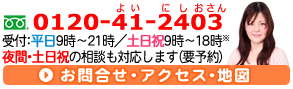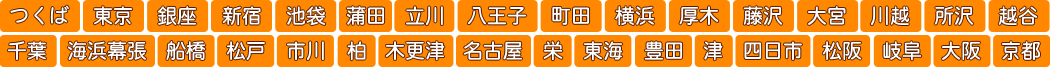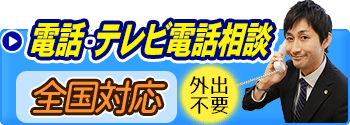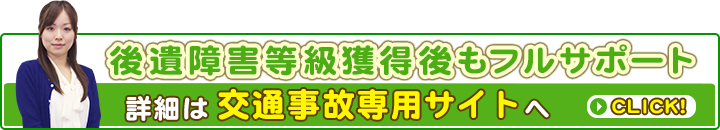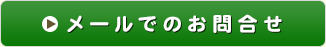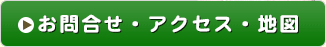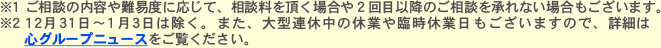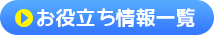大阪で後遺障害で弁護士をお探しの方へ

1 大阪の方が当法人に相談する場合
⑴ 大阪駅近くに事務所があります
弁護士法人心 大阪法律事務所は、大阪市北区梅田にある大阪駅前第3ビル30階に事務所を構えています。
大阪駅から徒歩5分・北新地駅から徒歩1分・東梅田駅から徒歩2分の場所に位置しているため、複数の路線からアクセス可能で、各地からご利用いただきやすい立地にある事務所です。
後遺障害でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
⑵ 電話でのご相談も承っております
来所するのに便利な立地にあるとはいえ、事務所に行くのは敷居が高いと思われている方や、来所する時間がなかなか作れないという方もいらっしゃるかもしれません。
当法人では、後遺障害についてお電話でのご相談も承っております。
大阪の事務所までお越しいただかずに相談することができますので、ご自宅から気軽にご利用いただけます。
ご相談の受付はフリーダイヤルまたはメールフォームから承っており、フリーダイヤルは土日祝日もお電話がつながりますので、まずはこちらにご連絡ください。
⑶ 夜間・土日祝日の相談にも対応
調整によって、夜遅い時間や、土日祝日に相談していただくこともできますので、弁護士に相談することを先送りにしてしまわずに、まずは一度お問い合わせいただければと思います。
早い段階から弁護士に相談し、対応などについてアドバイス等を受けていた方が、適切かつスムーズな事案解決につながる可能性が高まります。
2 後遺障害を弁護士に相談した方がよい理由とは
治療を終えても症状が残ってしまった方に対し、必ず後遺障害が認定されるわけではありません。
損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所という機関が書面で審査を行います。
参考リンク:損害保険料率算出機構・当機構で行う損害調査
後遺障害として認定されてもおかしくない場合であっても、申請時に不備があったり、診断書の内容が不十分であったりすると、後遺障害にはあたらないと判断されてしまうおそれがあります。
後遺障害が認定された場合に請求できる損害賠償があるため、認定の可否によって損害賠償額が大きく変わることになります。
認定された場合に請求できる項目として「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」が挙げられます。
後遺障害逸失利益とは、「被害者に後遺障害が残らなかったとしたら将来被害者が受けることができたであろう利益」のことをいいます。
これらを請求する際に、後遺障害等級が金額に大きく関係してきます。
そのため、後遺障害の申請を行う際には、後遺障害を得意とする弁護士に相談し、適切な等級認定の獲得に向けてサポートを受けることをおすすめします。
3 当法人は後遺障害を得意としています
交通事故の後遺障害に関する知識があり、日頃から後遺障害案件を取り扱っている弁護士であれば、適切な対応やサポートが期待できます。
当法人は、損害保険料率算出機構の元職員や保険会社の元代理人弁護士が在籍している強みを活かし、交通事故の後遺障害について内部研修を行う等、ノウハウを身に付けられるようにし、難易度の高い案件を含め、後遺障害に関する多様なお悩みに対応できるようにしています。
後遺障害の適切な等級認定の獲得を目指し、尽力いたしますので、交通事故による後遺障害は当法人の弁護士にお任せください。
後遺障害の認定を受けるか否かは賠償額に関わる部分となりますので、後悔することのないように、少しでも不安なことがありましたら、示談に応じる前に、まずはお気軽に当法人にご相談ください。
4 どなたにも気軽にご相談いただけるように
当法人は、交通事故の後遺障害に関するご相談は、弁護士費用特約をご利用いただけます。
弁護士費用特約は、保険会社から弁護士費用の支払いを受けることができるものになりますので、これを利用することで、費用の心配をすることなく、弁護士にご依頼いただけます。
よほど高額な場合を除き、保険の範囲内で足りることが大半です。
弁護士費用特約がない場合でも、後遺障害のご相談は原則無料で承っておりますので、弁護士費用の負担を不安に思わずに、まずは一度ご相談いただければと思います。
また、どなたにも気軽にご利用いただけるように、無料で妥当な後遺障害等級を予測するサービスや、損害賠償額を算定するサービスをご用意しております。
弁護士に相談しようか迷っているという方は、まずはこれらのサービスの利用をご検討ください。
後遺障害の申請ではどのようなことに気をつけるべきか
1 事前認定か被害者請求か

⑴ 後遺障害の申請方法
自賠責保険への後遺障害申請の申請方法は、おおまかに分けると2通りあります。
被害者自身もしくは被害者が委任する弁護士等に任せる被害者請求の方法と、相手方任意保険会社に任せる事前認定の方法です。
⑵ 事前認定は必ず不利になるのか
事前認定は相手方任意保険会社に任せることになるので、後遺障害申請時に相手方任意保険会社の担当者に被害者の不利になる資料を混ぜられて、適切な認定等級がされないおそれがあるなどと紹介されることもありますが、事前認定の場合に必ずそうされるとも限りません。
不利な資料を混ぜられようが、通院日数や通院期間、レントゲン画像やMRI画像の状態が変更されるわけではありませんので、病院へ適切に通院していれば等級が認定されるときももちろんあります。
⑶ 被害者請求であっても等級認定がされない場合もある
逆に、被害者請求であろうと事故態様や適切に通院していない場合などは残念ながら後遺障害の等級認定がされないこともあります。
⑷ 弁護士に判断をお任せを
被害者請求でやるべきか、事前認定でやるべきかは、弁護士の専門的判断に任せてみるのが一番です。
弁護士費用特約が付いてない方で、戦略的に事前認定をしてみても、無事に適切な等級認定がされた方はたくさんいらっしゃいますので、どちらの方法で申請するのか迷われている方は、まずはご相談ください。
2 実質面
⑴ 症状固定日までの期間
ひとついえることは、後遺障害というからには、今後一生その部位にその症状が残ってしまうであろうと認定してもらう必要があります。
ですので、たとえば、事故から半年未満で一旦区切って後遺障害申請をしたところで、もう少し治療を続ければその後遺症は治る可能性があるのではないかと判断され、後遺障害の等級をつけてもらえないのです。
目安としては、どんな後遺障害でも、原則として最低事故から半年以上たってから症状固定にしてもらって、後遺障害申請しないと、等級「非該当」という結果が返ってくる可能性が高いです。
⑵ 自覚症状欄
詳細は、実際に当法人の弁護士に相談して確認していただきたいのですが、自覚症状欄にある記載がされていると、ただそれだけで、後遺障害の等級認定がされる可能性が激減するというワードがあります。
自覚症状欄については、医師に伝える際に注意しておくべきポイントがありますのでお気をつけください。
⑶ 「障害の増悪、緩解の見通し」
この欄についても、ある記載をされると、ある等級の認定がされにくいという文言があります。
3 後遺障害の相談は弁護士法人心 大阪法律事務所まで
後遺障害診断書の記載について注意しておくべきポイントの詳細は、実際に事故態様、負傷内容、治療経過などをお伺いした上で、弁護士からアドバイスさせていただきますので、後遺障害についてご不安に思われている方は、まずは弁護士法人心大阪法律事務所までご相談ください。
交通事故を多く取り扱っている弁護士が相談に乗らせていただきます。
むちうちが後遺障害に認定されるケース
1 むちうちでも後遺障害に認定されることはある

後遺障害での「むちうち」は、首の痛みやしびれに限らず、肩、腕や足のしびれなどでもむちうちと表現されます。
これらのむちうちは、一定の基準に該当すれば、後遺障害等級14級や12級と認定されることはあります。
もっとも、むちうちで12級が認定されるケースは14級よりはかなり少ないと思ってください。
2 後遺障害の認定はどこが行うのか
むちうちの後遺障害を認定するのは、損害保険料算出機構に属する自賠責保険調査センター調査事務所という第三者機関が行うことになります。
よく、通院先の医師から後遺障害診断書を作成してもらったことで後遺障害の認定をしてもらったと勘違いされる方もいらっしゃいますが、後遺障害診断書は、自賠責保険調査センター調査事務所に後遺障害として認定してもらうために必要な書類のひとつに過ぎません。
また、上記のとおり、後遺障害の認定は第三者機関である自賠責保険調査センター調査事務所が行うことから、むちうちのように他覚的所見に乏しい症状を、いかに後遺障害として認定してもらえるかが非常に重要なポイントになります。
3 14級が認定される場合
⑴ 事故の衝撃の大小
痛みやしびれが続いている部位に、事故でどの程度の衝撃が加わったのかを判断するために、事故車両の修理金額が一つの参考とされます。
とはいえ、修理金額が大きければ必ず14級が認定されるというわけではありません。
⑵ 被害者の年齢
年齢が若いほど体の回復力が高いと考えられているため、10代~20代の方で14級が認定されることはまれです。
おおむね40代を超える方は、若い方と比べますと、14級が認定されやすいといえます。
しかし、年齢が高くても14級が認定されない場合はもちろんあります。
⑶ 通院頻度や通院期間
14級が認定されるためには、常時、局部に神経症状(痛みやしびれ)が残存すると認定されなければなりません。
そうすると、月に数回程度であれば、それほどひどい神経症状であると認定されにくくなりますし、通院期間も、症状固定までに6か月未満の場合も、もう少し通えば回復してくるのではないかと思われ、14級が認定される可能性がかなり低くなってきます。
⑷ 症状の一貫性
14級が認定されるためには、事故直後より一貫してその部位に痛みやしびれが継続している必要があります。
そのため、事故から3週間後に痛みだした部位については、原則として14級が認定されることはありません。
⑸ 総合判断
14級が認定されるためには、上記⑴~⑷の要素を主に判断して、その他の事情もあわせて総合判断のうえ、決定されます。
4 12級が認定されるケース
むちうちで12級が認定されるケースは、14級に比べるとぐっと減ってきます。
例えば、骨折したところがあり、その部分の骨のくっつき具合が悪く、それが原因でその部分に痛みやしびれが生じているというように、医学的根拠による証明が可能な場合に12級が認定されることがあります。
後遺障害が非該当となったらどうすればよいか
1 後遺障害非該当の場合に必ずすべきこと
⑴ 非該当の結果
後遺障害非該当ということは、症状が完治せず後遺障害が残っているとして、その後遺障害について後遺障害等級認定の申請を行ったにも関わらず、自賠責保険で後遺障害等級が何も認定してもらえなかったということになります。
⑵ 当法人の強み
残存している症状について、自賠責保険で後遺障害等級認定を得られなかった場合には、その非該当との判断の妥当性を検証する必要があります。
自賠責保険の判断の妥当性の検証には、後遺障害等級認定についての知識と経験が必要となるところ、当法人は、弁護士と後遺障害申請専任スタッフがチームで検証を行っています。
そして、後遺障害申請専任スタッフは、実際に自賠責保険調査事務所で後遺障害等級を認定・審査していたスタッフが担当しています。
また、当法人には、後遺障害申請専任スタッフは複数名在籍しており、幅広い検証が可能となっています。
実際に後遺障害等級を認定・審査していたスタッフが非該当になった結果を検証すれば、その結果が妥当であるのか否か、妥当でないのであれば、異議申し立てをすれば適切な等級認定がされる可能性があるかなどの点で、的を得た検証が可能となります。
一方、後遺障害認定機関の内部で業務経験がない者が非該当の結果を検証したとしても適切な検証をすることが難しく、的外れな検証結果となることもあるでしょう。
2 当法人に相談する前に用意していただきたいもの
可能であれば、①後遺障害診断書のコピー、②後遺障害非該当の結果の用紙(「自動車損害賠償責任保険お支払い不能のご通知」などと書かれた書面)をご用意してください。
あとは、もう1種類の書類をご用意していただきたいのですが、この書類の存在を知っている弁護士はそう多くはないため、詳細は、ご相談時にご案内させていただきます。
3 むちうちで非該当になっている場合
頚部痛などいわゆる「むちうち」に起因する後遺障害については、自賠責保険で非該当と判断された原因が複数考えられます。
例えば、年齢が若すぎた、医療機関への通院回数・頻度が少なかった、車の損傷具合が軽微であった、症状の一貫性がなかったなどです。
当法人にご相談していただけましたら、異議申立てをして等級が認定される見込みがあるかの判断をさせていただきます。
4 申請し忘れていた項目について
残念ながら、後遺障害の認定システムは、労災や自賠責のシステムであって、医師会などが作成しているものではありません。
そのため、後遺障害診断書を作成してくださる医師が後遺障害の認定システムに詳しくない場合もありどんな被害者に対しても、常に完全な形での後遺障害診断書を作成してくれているわけでもありません。
ときには、申請すべき後遺障害を見落とし、後遺障害診断書への記載が漏れてしまっている場合もあります。
その場合には、その後遺障害を追加申請すれば、その後遺障害について適切な等級認定がされるケースがあります。
5 ご相談はなるべく早く当法人まで
特にむちうちの場合には、打ち切られたあとも、症状が残っているのであれば、通院を継続しておく必要があると思います。
後遺障害が残り、痛みが残存しているとどれだけ主張しても、通院して治療を継続していなければ、その主張は信用されにくいです。
通院継続の必要性は、弁護士などに指摘してもらわないとなかなか気付けないことかもしれません。
手遅れにならないためにも、後遺障害等級認定の申請についてご不安を感じておられる方は、速やかに弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談されることをおすすめいたします。
後遺障害が残った場合の成年後見制度
1 高次脳機能障害になった場合

交通事故による外傷で、脳に傷がついてしまって、高次脳機能障害の後遺障害を残してしまった方は、認知障害、行動障害、人格変化などが生じます。
その障害の程度が重い場合には、自己の財産を適切に管理できなかったり、契約などの法律行為をしっかりと理解したうえで契約することができなかったりといった支障が生じることになります。
このような高次脳機能障害の程度が重い方を保護するために、成年後見制度があります。
まず、成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
法定後見制度とは、高次脳機能障害などで判断能力が低下した際に、判断能力の程度に応じて、成年後見人、保佐人、補助人のいずれかが裁判所によって選任され、本人に代わって契約などの法律行為を行ったり、財産の管理を行ったりする制度です。
任意後見制度とは、上記と異なり、判断能力が低下する前にあらかじめ任意後見人と代わりに行ってもらう事項を決めておき、実際に判断能力が低下した際に、決めておいた内容につき任意後見人が事務を行うという制度です。
通常、交通事故によって高次脳機能障害が発生することを予測することはできませんので、高次脳機能障害になった場合には、法定後見制度による後見人の選任がなされるケースが多いです。
2 高次脳機能障害等級が1級~2級の場合
高次脳機能障害の等級は、一番重い1級から一番軽い9級までありますが、成年後見人を選任する必要があるのは、1級や2級の重い高次脳機能障害を残した場合です。
3級以下の場合には、保佐人が選任されたり、7級や9級程度では、そもそも補佐人すら選任する必要がない場合がほとんどです。
もっとも、成年後見人を付すかどうかは、主治医の見解を参考にしたうえで、家庭裁判所が最終的な判断を下します。
まずは、主治医の先生に相談してみることをおすすめいたします。
3 必ず成年後見人を選任しなければならないのか
高次脳機能障害1級や2級の方のご家族から、成年後見人を必ず付さなければならないのかと質問を受けることがよくあります。
我々弁護士としての見解は、成年後見人を選任しなければ、損害賠償請求事件に関して委任契約を弁護士と締結できませんし、保険会社も示談に応じてくれないことが多いため、必ず成年後見人を選任すべきだと考えます。
成年後見人を選任すると、被害者本人の財産は、成年後見人が管理することになり、財産状況などを家庭裁判所への報告が必要となります。
また、いくら被害者本人のために財産を支出しようとしても自由に支出できなくなります。
そのため、成年後見人を選任しないで、弁護士を契約する方法はないのかと聞かれることがよくありますが、そのような方法は残念ながらございません。
被害者様ご本人の利益保護のためにも、成年後見人を選任されることをおすすめいたします。
4 成年後見の申立て
成年後見の申立ては、ご家族様だけでも手続きは可能ですが、弁護士にご依頼いただくこともできます。
交通事故の示談交渉も、成年後見の申立て手続きも全て弁護士に任せたいという方は、当法人にお任せください。
後遺障害における将来介護費
1 将来介護費とは
交通事故により、治療を受けたものの後遺障害が残り、介護が必要な状態となった場合、将来の介護に必要な費用について不安に感じる方も多いと思います。
症状固定日以降にかかる将来の介護費用については、将来介護費としてまとめて賠償を受けることができます。
2 介護費用の日額について
⑴ 後遺障害等級1級、2級の場合の目安金額
ア 職業付添人の場合
「実費」が損害として認められるとされています。
ただ、実際のところは、無制限に認められるわけではなく日額1万円台での賠償が多く、日額2万円を超える場合は、①24時間体勢の看護が必要な場合や、②数時間ごとの体位変換が必要な場合など、比較的長時間の付き添いが必要な場合など、介護の負担が大きい場合に限られます。
イ 近親者介護の場合
赤本基準では日額8000円とされていますが、1級の場合は、日額8千円~1万円が多く、2級の場合は、日額5千円~8千円が認定されていることも多いです。
⑵ 後遺障害等級3級以下の場合の目安金額
3級以下になってくると、将来介護費まで認められるケースがぐっと減ってきます。
そのため、すべてのケースで将来の介護費用が認められるのではなく、個別的な介護の必要性及び相当性に応じて、数千円台の範囲で認められることになります。
3 将来介護費の計算方法
⑴ 計算方法
介護日額×365日×平均余命に対応するライプニッツ係数
ライプニッツ係数とは中間利息控除を行うための係数です。
中間利息控除が行われるのでは、将来の介護費用を前倒しで賠償を受けることになるため、先に賠償金を受け取ることで得られる利益を控除する必要があると考えられているためです。
⑵ 具体例
被害者が30歳(症状固定時年齢、平均余命52年)で、①母親が現在62歳で、67歳までの5年間は母親が介護(日額8000円)をするが、②それ以降の47年間は、職業付添人が介護(日額1万5000円)をする場合。
①8000円×365日×4.5797[※1]=1337万2724円
※1 母親が67歳になるまでの5年間のライプニッツ係数
②1万5000円×365日×(26.1662[※2]-4.5797)
≒1億1818万6088円
※2 平均余命52年に対応するライプニッツ係数
①+②=1億3155万8812円
4 弁護士にご相談を
将来介護費については、被害者の年齢がよほどの高齢でもない限り、長期間の介護費用を請求することになるため、日額の違いがとても高大きな賠償額の違いとなります。
将来の不安を補うための適切な将来介護費用について、ご本人様やそのご家族だけによる示談交渉では、勝ち取ることは難しいことが多いです。
高額かつ適切な賠償額を勝ち取るためには、交通事故の交渉に慣れている実績豊富な弁護士事務所にご相談されることが最善の方法といえるでしょう。
弁護士法人心 大阪法律事務所は、交通事故の案件を多く取り扱っております。
交通事故で突然大きな怪我を負われ、将来に大きなご不安を抱えておられ方のお力になれればと思っておりますので、お気軽に弁護士法人心のフリーダイヤルまでお電話ください。
後遺障害等級と慰謝料の関係
1 後遺障害等級について

⑴ 後遺障害の種類
後遺障害等級は、一番後遺障害の程度が重い1級から、一番程度が軽い14級まで定められています。
⑵ 1級の具体例
両眼が失明、両腕や両足が全く動かない、高次脳機能障害の一番程度が重い症状などがあります。
⑶ 14級の具体例
「局部に神経症状を残すもの」むちうち症が一番有名です。
2 後遺障害等級ごとの慰謝料の金額
慰謝料は、精神的肉体的苦痛を慰謝する金額であるため、程度の重い等級であるほど、慰謝料の金額も高額になります。
ア 大阪地裁における基準(通称「緑本」基準)
下記は、後遺障害等級ごとの関西地方の裁判所などで参考にされる後遺障害慰謝料の基準額です。
かっこ内の金額は、東京地裁における基準である通称「赤本」基準の金額を参考までにあげています。
1級:2800万円(2800万円)
2級:2400万円(2370万円)
3級:2000万円(1990万円)
4級:1700万円(1670万円)
5級:1440万円(1400万円)
6級:1220万円(1180万円)
7級:1030万円(1000万円)
8級:830万円(830万円)
9級:670万円(690万円)
10級:530万円(550万円)
11級:400万円(420万円)
12級:280万円(290万円)
13級:180万円(180万円)
14級:110万円(110万円)
※緑本の金額は、平成14年1月1日以降の事故についての基準です。
イ 示談段階の基準
上記アの基準は、訴訟(裁判)基準満額の基準です。
訴訟をすれば、裁判所が認定してくれる可能性が割と高い金額でもあります。
しかし、示談段階では、保険会社は、なかなか訴訟基準満額の金額をだしてくれることはないです。
よくある回答が、訴訟基準の8割~9割掛けしか出せないと回答されることが多いです。
3 併合14級の場合
むちうちで14級が2つ以上認定される場合があります。
例えば、①頚部痛で14級、②腰部痛で14級、あわせて「併合14級」と評価されます。
14級の後遺障害慰謝料は、110万円(※訴訟基準満額の場合)です。
14級一つだけの人は、110万円。
では、14級が2つ認定されている被害者は、110万円を超えて後遺障害慰謝料がもらえるのでしょうか?
残念ながら、14級がいくつ認定されていても、評価としては併合14級であって、訴訟をしたとしても、後遺障害慰謝料が110万円を超えることはあまりないケースがほとんどです。
4 適切な後遺障害等級を獲得するためには
後遺障害は、認定されるか否か、認定されるとして等級が一つ異なるだけで、賠償金が数百万円、場合によっては一千万円以上変わってしまうことがあります。
高次脳機能障害においては、医師が作成する神経系統の障害に関する医学的意見やご家族が作成する日常生活状況報告などの内容で、実際の症状よりも軽いものと評価される記載があれば適切な後遺障害等級が認定されないことがあります。
むちうち症においては、非常時痛と評価される記載があれば、後遺障害が認定されないことがあります。
適切な後遺障害等級が認定されるためにも、後遺障害申請のための書類作成時の注意点や、受診時の注意点を知っておくことが大切です。
そのため、適切な後遺障害等級を獲得するためには、後遺障害に詳しい弁護士にできる限り早い段階で相談することが大切です。
後遺障害認定の結果に不服がある場合
1 認定結果の妥当性の検討
後遺障害等級認定の結果が保険会社から届いたら、結果に不服がある場合はもちろん、認定結果が妥当であるかどうかわからないような場合も、まずは、当法人まで、ご相談ください。
その結果が妥当であるか否かについて、交通事故を多く取り扱っている当法人の弁護士と後遺障害等級認定機関(損害保険料率算出機構、紛争処理機構)に長年勤めていたスタッフらで検討し、認定結果が妥当でない場合はどのような等級の認定を得られる可能性があるのかについて弁護士が相談に乗らせていただきます。
2 異議申し立て
⑴ 認定結果が妥当な場合
認定結果が妥当な場合は、異議申し立てをしても、等級認定や昇給する見込みがないため、異議申し立てを行う時間は無駄となってしまう可能性があります。
よくあるのが、①症状がある部位に骨折等の他覚所見はないが、「12級13号が何故認定されないのか?」という質問や、②医療機関への通院回数が少なかったが、「痛みがあるのに後遺障害等級が認定されないのはおかしい」という質問です。
また、③外貌醜状の場合に、認定基準の大きさや長さに達していないにも関わらず、「傷跡が残っているのに等級認定されないのはおかしい」という質問や、④可動域制限の数値が認定基準に達していないにもかかわらず、「可動域制限があるのに、この制限に関する等級認定されないのはおかしい」という質問もあります。
後遺障害等級が認定されるためには、そもそもの大前提として、自賠責保険の後遺障害の認定基準に該当する必要があるのですが、身体に少しでも症状が残っていれば、それが後遺障害の等級が認定されるものだと勘違いされている方もいらっしゃいますが、必ずしもそうではありません。
⑵ 認定結果が妥当でない場合
認定結果が妥当でない場合には、異議申し立てや、そもそも申請していなかった部位の症状があった場合には追加申請の是非を検討します。
場合によっては、さらなる通院の継続や、追加検査などをしていただく必要がございます。
3 紛争処理機構や訴訟へ移行
異議申し立てや追加申請で期待した結果が得られなかった場合には、紛争処理機構へ不服を申し立てたり、訴訟を視野に入れたりします。
ただ、異議申立てや追加申請を行っても期待した認定結果が得られていない場合は、訴訟などを行ったとしても期待する後遺障害の認定を得られる可能性は厳しい見通しとなることが多いです。
そのため、通院中、初回の後遺障害等級認定の申請時や異議申立て時からしっかりと準備を行っておくことが重要です。
4 弁護士法人心にご相談ください
弁護士法人心は後遺障害等級認定の申請のサポートについて力を入れております。
後遺障害等級認定についてご不安に思われている方は、早めにご相談ください。
また、異議申立ての必要性についても相談に乗ることができますので、後遺障害等級の認定結果が妥当なものか否か知りたいといった方もお気軽にご相談ください。
後遺障害等級認定における当法人の強み
1 後遺障害認定機関で実際に働いていたスタッフが在籍

⑴ 後遺障害等級認定の仕組み
後遺障害等級の認定機関は、「損害保険料率算出機構」という機関が保険会社から委託を受けて集中的に行っています(参考リンク:自賠責の損害調査・損害保険料率算出機構)。
つまり、後遺障害等級認定は、病院(医師)や任意保険会社がするわけではありません。
⑵ 後遺障害等級認定について一番詳しい人物とは?
そうすると、後遺障害等級認定については、実際に審査を担当している損害保険料率算出機構の職員が一番詳しいということになります。
⑶ 当法人には、損害保険料率算出機構の元職員が在籍
当法人には、実際に後遺障害等級認定を担当していたスタッフが複数在籍しております。
その中には、審査担当者に研修を行ったり、後遺障害等級の認定基準についての内部基準を策定したりして、高次脳機能障害やむち打ち以外の後遺障害についても詳しいスタッフがいます。
他にも、異議申し立て案件を中心に扱ってきたスタッフや、後遺障害等級認定課長を務めていた者など、損害保険料率算出機構に長く勤めてきたスタッフもいます。
実際に後遺障害等級認定を担当・関与していたスタッフは、どのような場合に、どのような後遺障害等級が認定され、または、認定されないのかを知り尽くしているといっても過言ではありません。
⑷ 当法人の弁護士との連携
当法人の交通事故担当弁護士は、このスタッフと連携し、むちうちの後遺障害から、それ以外の高次脳機能障害から、可動域制限やその他のあらゆる後遺障害について、協議しながら、後遺障害申請や異議申し立てを行っております。
⑸ 異議申し立て
1回目の後遺障害申請で、適切な等級が認定されなかった場合には、もう一度後遺障害申請をして異議申し立てをすることが考えられます。
この際に、どのようにすれば、今度は適切な後遺障害等級が認定されるかのポイントを押さえたうえで、異議申し立てをしなければ、適切な等級認定がなされないことはいうまでもありません。
実際に後遺障害等級を認定審査してきた職員が異議申し立てのポイントについて一番詳しいといえます。
当法人の交通事故担当弁護士は、後遺障害等級認定を担当していたスタッフから異議申し立てのポイントのアドバイスを受けたうえで、異議申し立てをしていきますので、適切な異議申し立てを行うことが可能なのです。
2 交通事故案件の取扱件数が多い
交通事故の取扱件数が多いということは、交通事故の知識やノウハウを集積しやすい傾向にあります。
当法人は、交通事故の取扱件数が非常に多く、交通事故案件に関して、豊富な知識とノウハウを有しています。
むちうち案件、骨折案件、高次脳機能障害案件など様々な案件を対応しており、その後遺障害等級認定申請において、気を付けるべき点などについて豊富な知識を有しています。
3 交通事故を集中的に取り組む弁護士が交通事故案件を対応する
弁護士の中には、様々な分野を対応する弁護士が存在する一方、特定の分野を集中的に対応する弁護士もいます。
様々な分野を対応する弁護士は、特定の分野(たとえば、交通事故など)を集中的に取り組む弁護士と比べて、特定の分野に関しては、経験を積みにくい傾向にあり、結果的に、特定の分野に関する知識やノウハウを集積しにくい傾向にあります。
そこで、当法人では、少しでも相談者の方や依頼者の方に質の高いリーガルサービスを提供したいと考え、特定の分野を集中的に取り組む弁護士が、特定の分野を対応する担当制(部門制)を採用しています。
そのため、交通事故を集中的に取り組む弁護士が交通事故案件を対応することになります。
担当制(部門制)を採用することで、弁護士が特定の分野に関するより多くの知識や経験を修得しやすくなり、より質の高いリーガルサービスを提供できることになります。
後遺障害について弁護士に依頼する場合の費用について
1 はじめに
弁護士費用特約に加入されている方は、弁護士に依頼した場合にかかる費用を弁護士費用特約で全て賄うことができるため、自己負担なく弁護士に依頼することが可能なことが多いです。
弁護士費用特約にご加入されていなかったり、加入していても使えなかったりする場合は、弁護士費用は自己負担となってしまいます。
では、後遺障害について弁護士に依頼する場合、どのような費用がかかるのか以下でご説明いたします。
2 相談料
相談料は、弁護士と契約する前に相談した分に対して、発生します。
相場は、30分ごとに5500円(税込み)程度です。
弁護士費用特約が使える方は、保険会社が負担してくれます。
なお、弁護士法人心では、弁護士費用特約が使えない方もご相談していただきやすいように、弁護士費用特約が使えない方の相談料は原則無料となっております。
3 着手金
⑴ 弁護士費用特約が使える場合
着手金は、依頼を受けた事件に着手するにあたって発生する弁護士費用となります。
着手金の額は、相手方に請求をかけた金額(経済的利益)によって変わります。
例えば、500万円を相手方に請求した場合の着手金は以下のとおり、算定されます。
500万円×5%+9万円+税=34万円+税
〇%という数字は、請求する金額に対して変動するものであって、契約書に定められております。
⑵ 弁護士費用特約が使えない場合
当法人では、原則、いただいておりません。
4 弁護士報酬
⑴ 弁護士費用特約が使える場合
獲得できた金額(経済的利益)に応じて発生する弁護士費用が、弁護士報酬となります。
例えば、500万円を獲得できた場合には、以下のように弁護士報酬が算定されます。
500万円×10%+18万円+税=68万円+税
〇%という数字は、獲得できた金額によって変動するものであって、あらかじめ契約書に定められています。
⑵ 弁護士費用特約が使えない場合
事案の難易度に応じて、決められます。
5 タイムチャージ料(時間制報酬)
着手金・報酬金方式になじまない場合には、1時間当たり〇万円としてタイムチャージによる弁護士費用を定める場合もございます。
一般的には1時間当たり2万円+消費税程度と設定されていることが多いです。
タイムチャージ料についても弁護士費用特約が使える場合は、上限時間に達するまでは弁護士費用特約で賄えます。
6 実費
書類の郵送代、書類のコピー代、FAX代、訴訟を提起する場合などの収入印紙代などがかかります。
これらの費用も弁護士費用特約が使える場合は、弁護士費用特約で賄うことができます。
7 出張料、出廷費用
弁護士が、事故現場へ行って調査するとか、病院に行って医師と面談する場合などの出張費用、訴訟になっている場合の裁判所への出廷費用などがかかります。
これらの費用も弁護士費用特約が使える場合は、弁護士費用特約で賄えることが多いです。
8 後遺障害申請特有の費用
⑴ 当法人がいただく費用
後遺障害に関連する特別の費用は、当法人では原則としていただいておりません。
例えば、異議申し立てをする費用が、手数料で〇万円かかるということは、原則ありません。
⑵ 病院に支払う費用
後遺障害申請の場合、後遺障害診断書作成料を病院に払ったりしますが、これは、当然ながら病院に支払うものであって、弁護士側が受け取る費用ではありません。
また、異議申し立ての際にカルテが必要となる場合に、カルテ開示をするときなどは、病院にカルテ開示手数料などがかかったりします。
この費用は、病院によってまちまちであり、コピー代程度で済む病院もあれば、数万円程度の手数料が取られてしまう場合もあります。
9 相談はお気軽に
大阪にお住まいの方は、面談相談でもお電話での相談でも可能ですので、当法人のフリーダイヤルまでお電話ください。
交通事故を多く取り扱っている弁護士が相談に乗らせていただいます。
適切な後遺障害の賠償を得るために大切なこと
1 結論

適切な後遺障害の賠償を得るために大切なことは、ずばり、交通事故について詳しい弁護士に依頼することです。
交通事故に詳しいとは、①適切な後遺障害等級認定を得るためのノウハウを有し、②交通事故の示談交渉や訴訟戦術に長けていることです。
適切な後遺障害等級認定がなされていることは、交通事故の適切な賠償を得るためには重要なポイントとなります。
なぜなら、適切な後遺障害等級の認定を得られていなければ、数百万円~数千万円も賠償金が低くなってしまうという事態が生じるからです。
また、示談交渉や訴訟戦術に長けている弁護士でなければ、本当はもっと賠償金が取れていたのにとうこともあります。
以下、具体的にご説明いたします。
2 ①適切な後遺障害等級の認定
⑴ 後遺障害申請に精通した弁護士に依頼すべし
後遺障害申請は、必要な書類を集めれば誰でも申請可能です。
ですが、後遺障害の等級は、書面に書かれている内容をもとに審査されますので、書面に書かれている内容が不適切であったりすると適切な後遺障害等級の認定は得られません。
そのため、後遺障害申請について、精通した弁護士に頼み、不適切ないし不十分な状態で後遺障害申請することを防ぐことが重要です。
⑵ 後遺障害申請に精通した弁護士とは?
では、後遺障害申請に精通した弁護士とは、どのような弁護士を指すのでしょうか?
もちろん、後遺障害申請に関して何百件、何千件と申請経験がある弁護士は、後遺障害申請に精通しているといえるでしょう。
ただ、後遺障害申請を行った件数が多いという以上に、後遺障害等級認定機関である「損害保険料率算出機構」の内部事情(認定基準や認定システム)にまで精通している弁護士が、後遺障害申請について、より精通しているといえます。
当法人のスタッフには、後遺障害認定の審査機関に長年勤めていたスタッフが複数名在籍しており、その者たちと連携して対応しますので、当法人の弁護士は申請件数以上により後遺障害申請に精通しています。
当法人は、適切な後遺障害等級の獲得に力を入れておりますので、後遺障害等級認定に不安を抱かれている方もご安心ください。
3 ②示談交渉や訴訟戦術に長けている弁護士とは
⑴ ただベテラン弁護士というだけでは足りない
示談交渉や訴訟戦術に長けている弁護士とは、ベテランの弁護士という条件だけでは足りません。
「弁護士経験年数が長いベテランの弁護士であると安心なのではないか?」という思考には注意が必要です。
交通事故事件は、損害賠償請求事件のなかでも後遺障害、過失割合、損益相殺、様々な保険など多くの論点が出てくる分野であり、ベテランの弁護士であるから交通事故の対応に慣れているとは言い切れません。
当法人の交通事故担当弁護士は、通常、年間数百件は交通事故案件を取り扱っておりますが、交通事故をメインに扱っていない当法人所属以外の弁護士は、交通事故案件に限ってみると年間数件ほどしか扱っていない場合もあります。
そうすると、弁護士経験年数が比較的浅い当法人所属の弁護士の方が、他の事務所のベテラン弁護士よりも、交通事故案件の処理件数は上回っているという現実があります。
交通事故の取り扱い件数が重要です。
⑵ 結果にこだわっている弁護士であるかどうか
弁護士の性格も様々です。
強気な弁護士、弱気な弁護士、理論派な弁護士、感覚派な弁護士など。
そのなかでも結果(依頼者の意向に沿った結果)にこだわっている弁護士は、依頼した場合に満足のいく結果を得やすいです。
結果にこだわるとは、例えば、依頼者の方の意向が、妥協せずに可能な限り高い賠償金を受け取りたいというものであった場合は、示談段階でも妥協した金額でまとめず、裁判も辞さない強気な交渉を行い裁判基準での慰謝料を獲得することを指します。
また、依頼者の方の意向が、裁判を避けつつある程度の賠償金を得たいとのことであれば、経験やノウハウを生かし、裁判にならない範囲で、交渉によって裁判基準に近い金額で慰謝料を獲得することを指します。
もちろん、依頼者の方が早期解決を希望するのであれば、その意向に沿って早期解決に持っていける弁護士が結果にこだわっている弁護士と言えます。
ただ、状況によっては、早期解決と訴訟基準と同額程度での示談を両立させることは難しいこともあります。
結果にこだわっている弁護士に依頼しましょう。
4 ご相談は当法人まで
大阪にお住まいの方で、適切な後遺障害等級認定を目指したい方、示談交渉や訴訟戦術に長けている弁護士にご相談されたい方は、当法人のフリーダイヤルまでお電話ください。
後遺障害について弁護士に依頼すべき理由
1 適切な賠償金額を得るために
交通事故に遭い、辛い思いをされた方の中には適切な補償や賠償を受けたいと考える方は多くいらっしゃいます。
まして、後遺障害が残ってしまったのであれば、適切な補償や賠償を受けたいと考えることが自然です。
後遺障害に関する賠償金は、認定される後遺障害の等級によって金額が大きく変わります。
そのため、適切な後遺障害等級を獲得することが適切な賠償金を得るうえで大切です。
2 適切な後遺障害等級を獲得するために弁護士に依頼する理由
⑴ 後遺障害等級認定申請は専門性が高い
後遺障害等級認定申請の認定基準のうち重要な部分は、基本的には外部に公開されていない情報になります。
後遺障害等級認定申請の認定は、損害保険料率算出機構が行いますが、この審査は書面審査が中心で、その書面の記載内容などが不適切な場合には、適切な後遺障害等級が認定されないことも多くあります。
たとえば、むちうちの症状(首の痛み)が残存した方で実際の症状は常時痛であり、天気の悪い日により増悪する症状であるにもかかわらず、後遺障害診断書に天気の悪い日に痛みが出ると記載されて後遺障害が認定されなくなってしまうことや高次脳機能障害で実際に就労が全く不可能な状態になっているにもかかわらず、ご家族の方が作成した日常生活状況報告で実際より軽く受け取られる記載があることから適切な後遺障害等級を得られないことなどがあります。
適切な知識やノウハウを得ずに後遺障害等級認定申請を行ってしまうと適切な後遺障害が認定されないこともあるため、後遺障害等級認定申請に詳しい弁護士に依頼することが大切です。
⑵ 被害者請求がおすすめ
後遺障害等級認定申請は、任意保険会社経由で行う事前認定の方法と被害者やその代理人弁護士などが行う被害者請求の方法があります。
事前認定では、必要書類以外の書類において、症状を適切に反映した治療関係の書類が提出されないことや不適切な記載内容の書類が提出されてしまうことがあるため、被害者請求の方がオススメです
もっとも、被害者請求を行う場合には、書類の取り付けを被害者自身が行わざるをえなくなるため、負担に感じられる方も少なくありません。
また、提出書類の判断に迷うこともあります。
そこで、後遺障害に詳しい弁護士に依頼して、書類の取り付けと選別を依頼することや様々なアドバイスを受けることが大切です。
3 適切な損害賠償額の獲得のためにも弁護士に依頼することが大切
適切な後遺障害等級が獲得できていたとしても、保険会社は、弁護士が介入していない場合には相場より低い示談金しか提案しないことも多いです。
したがって、示談交渉を交通事故に詳しい弁護士に依頼することが大切です。
4 弁護士法人心にお任せください
⑴ 後遺障害等級認定申請に詳しい
後遺障害等級認定申請の認定基準のうち重要な部分は、基本的には外部に公開されていない情報になります。
そのため、交通事故を集中的に取り扱っている弁護士であっても、後遺障害等級認定申請に詳しくない弁護士は多くいます。
したがって、損害保険料率算出機構の元職員がいる法律事務所や後遺障害等級認定申請の経験が豊富な弁護士から適切なアドバイスを受けることが大切です。
この点、当法人のスタッフには、後遺障害等級認定機関である損害保険料率算出機構において、重要なポストで長年勤務して、何千件もの後遺障害事案を扱っていたスタッフが在籍しておりますので、当法人は、様々な後遺障害事案について、十分な知識と経験を有している特徴があります。
⑵ ノウハウや実績多数
当法人では、これまでに、後遺障害申請を数千件規模で行ってきた実績があります。
当法人が関与した後遺障害申請については、その結果が妥当であるか、妥当でなければ、異議申立てにより、適切な等級獲得の可能性を常に模索してきましたため、多くのノウハウの蓄積があります。
⑶ 後遺障害申請のご依頼は当法人まで
上記のとおり、当法人は、高度の専門性を有する後遺障害申請について、専門性を有しているだけでなく、長年蓄積したノウハウや実績が兼ね備わっている法律事務所です。
後遺障害の高度な専門性をよく理解せずに、真に後遺障害申請に精通した法律事務所に後遺障害申請を依頼しなければ、適切な後遺障害等級の獲得が危ぶまれてしまうことにもなりかねません。
後遺障害申請をご検討の方はぜひ当法人にお任せください。
高次脳機能障害の後遺障害等級認定のポイント
1 高次脳機能障害の等級と注意点

高次脳機能障害(以下、「高次脳」と略記。)については、後遺障害等級は、1級1号、2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号があります。
高次脳の症状が全くない場合で、脳に傷が残っている場合には、脳挫傷痕の残存が12級13号と評価されることがあります。
その症状の程度によって高次脳機能障害の後遺障害の等級は異なり、1級1号は「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」、2級1号は「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」、3級3号は「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」、5級2号は「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」、7級4号は「神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」、9級10号は「神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」です。
自賠責保険会社による後遺障害等級認定では基本的には、書面によりその症状を判断するため、作成された書面の記載内容によって等級が大きく異なってしまうことも少なくありません。
つまり、適切な等級を得るためには適切な症状を記載された書面が作成されるように対応していくことがとても大切です。
とにかく早い段階で高次脳機能障害に詳しい弁護士に相談して、適切なアドバイスを受けることが大切です。
2 被害者請求で確実に適正な等級認定を目指していく
高次脳機能障害の後遺障害申請については、被害者請求(被害者側から自賠責保険会社に対して申請する方法)が好ましいです。
なぜなら、事前認定(相手方保険会社が行った後遺障害申請)では、適切な症状が記載されていない書面が提出されてしまうことや、不適切な内容が記載された書面が提出されてしまい、結果として、適切な等級が認定されない可能性があるためです。
高次脳機能障害に詳しい弁護士に依頼して、被害者請求で後遺障害申請を行っていくことをおすすめいたします。
3 ご家族の方が注意しておくべき点
⑴ 入院中
被害者の方が入院中に気付いた事故前と変わった点のすべての症状(怒りっぽくなった、子供っぽくなった、何度も同じ話をするようになったなど)を躊躇せずに、医師や看護師に繰り返し伝えるようにしてください。
退院時には、窓口で入院記録・看護記録の写しを入手しておくとよいでしょう。
⑵ 退院後
必ず、定期的に脳神経外科を受診し、画像診断を行ってもらい、事故前と変わった症状などを医師にしっかりと伝えるようにしておいてください。
⑶ 後遺障害申請前
ア 医療機関に記入してもらう書類があります。
①頭部外傷後の意識障害についての所見
②神経系統の障害に関する医学的意見
イ 被害者の家族又は介護者に記入してもらう書類
③日常生活状況報告書
等級(障害の程度)は家族が作成する「日常生活状況報告」で決まるといっても過言ではありません。
そのため、記載する前に高次脳機能障害に詳しい弁護士のアドバイスを受けたほうが良いのはもちろんですが、作成後も、高次脳機能障害に詳しい弁護士にチェックしてもらうことが大切です。
その他、症状固定時期が高校生までの場合、「学校生活の状況報告(学童・学生用)」も担任の先生等に記入してもらう場合もがありますが、担任の先生によっては、家族に気遣って遠慮がちな記載をしてしまうこともあり得ますので特に注意が必要です。
4 その他注意点
脳に外傷を負っている場合には、本人が気づかないうちに眼、耳、鼻、口に障害が残っている場合もあります。
その場合には、早い段階で、眼、耳、鼻、口に異常がないかを検査してもらう必要があります。
高次脳機能障害の被害の方は、ご自分では気づかない場合もありますので、ご家族の方が、積極的に主治医に相談し、眼科や耳鼻科などの医師を紹介してもらってください。
5 高次脳機能障害のご相談は弁護士法人心まで
高次脳機能障害が疑われるケースでは、早い段階から、高次脳機能障害に詳しい適切なアドバイスができる弁護士の関与が必須となります。
後でいいでは手遅れになる場合もありえますので、ご相談はお早目にされることをおすすめいたします。
後遺障害等級認定とは
1 後遺障害等級とは
自動車損害賠償保障法(以下、「自賠法」と略します。)施行令に規定されている別表第1及び第2の基準に該当する後遺障害であれば、その基準に応じて、後遺障害等級が認定されます。
等級は一番程度の重い1級から軽い14級まで規定されています。
後遺障害等級認定の申請をしたときに事故前にはなかった身体の異変が残っていても後遺障害等級が認定されないことがありますが、それは、後遺障害等級の認定機関である「自賠責が基準に該当しないと判断したから」になります。
2 後遺障害等級認定機関
後遺障害の等級認定の申請は、相手方加入の自賠責保険会社に対して行います。
自賠責保険会社は、申請を受け付けたら、損害保険料率算出機構という後遺障害等級認定の審査機関に審査を出します。
この損害保険料率算出機構とは、後遺障害等級に該当するかどうかを専門的に判断する機関です。
後遺障害等級は、医師が決めるのではなく、この損害保険料率算出機構が決めます。
そのため、医師が作成した後遺障害診断書に後遺障害が残存していると記載されていたとしても、審査の結果、自賠責保険では後遺障害等級が認定されないことがあります。
当法人には、この損害保険料率算出機構に在籍していたスタッフがおり、当法人の交通事故担当弁護士は、当該スタッフとともに後遺障害等級認定の申請を行っておりますので、後遺障害等級認定の基準に関する知識やノウハウなどを持ち合わせています。
当法人では、正確な情報に基づいた後遺障害等級認定のサポートを行っておりますので、ご安心ください。
3 後遺障害申請について
適切な後遺障害等級認定がなされるためには、適切な資料収集が必要となります。
例えば、むち打ち症の方の場合、レントゲン画像だけでなく、MRI画像まであると後遺障害申請時に不利に扱われることを防げる場合もあり、治療期間中にレントゲン検査に加えてMRI検査も受けておいた方が良いことがあります。
後遺障害申請については、保険会社に任せてはダメ、弁護士に依頼した方が良いと聞いたことがあるかもしれませんが、全部が全部そうとは限りません。
弁護士費用特約が使用できない場合や他の諸事情により、保険会社に任せて(「事前認定」と呼ばれています。)後遺障害等級認定の申請を行っても問題ない場合もあります。
被害者請求(被害者本人や被害者から委任を受けた弁護士が代理人となって申請する場合)か事前認定のどちらで後遺障害等級認定の申請をした方が良いかは、高度で専門的判断を要しますので、後遺障害等級認定の申請を検討されている方は正しい知識を持った、交通事故を得意とする弁護士までご相談ください。
4 ご相談は当法人まで
大阪やその周辺にお住まいの方で後遺障害等級認定について疑問なことやご不安なことがおありであれば、まずは当法人のフリーダイヤルまでご連絡ください。
交通事故被害者の方からのご相談は原則無料で受付けております。
ご相談の際は、交通事故を担当している弁護士がそれぞれの事情に応じた、具体的アドバイスをさせていただきます。
後遺障害申請を弁護士に依頼した場合の解決までの流れ
1 申請準備

⑴ 申請に必要な書類
後遺障害申請には、交通事故証明書、事故発生状況報告書、自賠責様式の診断書・診療報酬明細書(レセプト)、自賠責様式の後遺障害診断書、レントゲンやCT、MRIなどの画像CD-Rなどを用意する必要があります。
⑵ 申請の準備に必要な期間
診断書や診療報酬明細書は、相手方保険会社が治療費を負担している場合は、月毎に病院が作成して、相手方保険会社に送付していることがほとんどです。
通常は、当月の診断書・診療報酬明細書は、翌月の中旬以降に病院が作成することが多いため、保険会社を通じて診断書・診療報酬明細を手に入れる場合は、通院終了後、1か月程度かかります。
また、後遺障害診断書は、症状固定日以降に医師に残存している症状を伝え作成を依頼することになりますが、1週間~1か月くらい時間がかかる場合が多いです。
そのため、通院が終わればすぐに後遺障害申請ができるというわけではなく、申請の準備には1か月程度はかかります。
2 申請と申請結果
上記書類やその他の必要書類が全てそろいましたら、事故証明書に記載してある相手方が加入している自賠責保険会社の自賠責保険金請求窓口まで送付します。
申請したあと、後遺障害等級認定の結果が判明するまでに、おおむね1か月半から3か月程度かかることが多いです。
自賠責が、送付した書類だけでは結果を出すための資料が不足していると考える場合は、医療機関などに医療照会をかけることもあります。
この際、自賠責の医療照会に対する病院からの回答に時間がかかる場合には、その分審査に時間を要するため、自賠責からの結果が出るまで、4か月から半年程度かかることもあります。
3 異議申立ての検討
後遺障害の結果が判明しましたら、当法人の後遺障害申請専任のスタッフ(元後遺障害等級認定機関である損害保険料率算出機構に長年在籍していたスタッフ)が、その等級が妥当であるか、認定されるべき等級が認定されているかどうかを弁護士とともに判断します。
後遺障害の結果が妥当であれば、そのまま相手方保険会社へ請求する損害額の算定に進みます。
後遺障害の結果が妥当でなく、自賠責保険へ異議申立てを行うことで、適切な後遺障害の等級の認定を得られる可能性がある場合は、依頼者の方の意向も踏まえて、異議申立ての準備に移ります。
異議申立ては、自賠責の結果に不服がある場合に、自賠責のどの判断にどのような不服があるのか理由を書いた書面などを提出し、もう一度、自賠責の後遺障害等級認定の審査を受ける手続きとなります。
4 異議申立てと結果判明までの期間
異議申立てを行う場合は、異議申立て理由書の作成を行います。
また、異議申立て理由書の添付資料とするために追加で病院に診断書の作成を依頼したり、将来的に症状が回復する可能性があるといった理由で後遺障害の認定を得られていない場合には、症状の改善がないことを示すために後遺障害診断書作成後の依頼者の方の通院のカルテを取り付けたりすることもあります。
異議申立てをした場合に、その結果が判明するまでの期間は、初回申請よりも長い場合がほとんどです。
少なくとも2か月~4か月程度はみておく必要がありますし、それ以上の時間がかかることも当然あります。
5 損害額算定
初回申請や、異議申立ての結果、妥当な等級が認定されましたら(もしくは、非該当でもやむを得ないと判断した場合)、相手方保険会社へ当方の損害として請求する額の算定へと移ります。
損害額の算定には、資料の準備や争点の多寡や複雑さの程度にもよりますが、1週間から1か月程度(状況によっては2か月程度)かかります。
6 示談交渉
損害額の算定ができましたら、まずは、依頼者の方に請求する損害額をご確認いただきます。
そして依頼者の方から相手方保険会社へ請求する損害額について了承が得られたら、弁護士から相手方保険会社へ賠償金の請求を行い、示談交渉がスタートします。
弁護士が相手方保険会社と示談交渉を開始してから、示談が成立するまでの期間については、1~2か月程度で話がまとまることが多いです。
ただ、争点が複雑な場合や双方の主張する事実の隔たりが大きい場合は、話がまとまるまでに半年以上かかってしまうケースもあります。
どのような内容で示談をまとめるかは、弁護士が依頼者の方の意向を都度確認しながら進めていきます。
7 訴訟解決
話し合いがまとまらず示談が成立しない場合は、交通事故紛争処理センターへ申立てを行ったり、訴訟を提起したりすることになります。
訴訟なども弁護士が依頼者の方の代理人として手続きを進めます。
訴訟での解決の場合は、訴訟提起してから解決まで1年程度かかるケースが多いです。
当然ながら、もっと早く終わる場合や、もっと長くかかってしまうケースもあります。
8 ご相談は当法人まで
以上が、後遺障害についてご依頼いただいた場合の解決までの流れとなります。
後遺障害の申請手続きを被害者の方自身で適切に行うのは簡単なことではありませんので、早い段階で弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
当法人の大阪の事務所は、大阪駅前第3ビル30Fにあります。
ご相談いただきやすい立地ですので、「症状が重くて完治するか不安」「症状が残った場合は適切に後遺障害の判断を得たい」といった方は、弁護士法人心 大阪法律事務所まで、お気軽にお問い合わせください。
電話相談も可能ですので、外出が難しい方も安心してご連絡いただければと思います。
交通事故の後遺障害申請でお困りの方へ
1 後遺障害申請は小さなことで結果が大きく異なることがある
自賠責保険会社に対する後遺障害申請は、書面審査が中心で、診断書や後遺障害診断書などの治療経過に関する書類はもちろん、物損に関する資料や事故状況なども総合的に考慮して後遺障害の有無及び等級が認定されます。
後遺障害を申請したケースの中には、治療経過に関する診断書で、「改善傾向」との記載が多数記載されてしまっているために後遺障害が認定されないケースや、実際には常時痛であるにもかかわらず「雨の日に痛み生じる」(=雨の日でないと痛くない)などと記載されたために、後遺障害が認定されないケースなどがあります。
このように、小さなことと思えるような記載であっても、後遺障害が認定されるケースとされないケースがあることから、できる限り早期に交通事故や後遺障害に詳しい弁護士に相談することが大切です。
2 後遺障害に詳しい弁護士の見分け方
後遺障害申請に詳しい弁護士の見分け方としては、後遺障害等級認定機関で実際に働いた経験があるスタッフから話を聞ける状況にある事務所の弁護士ですと、後遺障害申請に本当に詳しいといえると思います。
後遺障害申請の件数だけそれなりに多かったとしても、自賠責などが、なぜ等級が認定されなかったのか、上位等級認定がされなかったなどの詳しい理由は教えてくれるわけではないからです。
その点、過去に実際に後遺障害等級認定機関の内部に従事していたスタッフが近くにいると、そのケースでは、どういう資料があればよいか、どのような修正・訂正が必要かなど、元後遺障害等級認定機関の生の声が聴けるわけです。
このような環境下にある弁護士ですと、自然と、後遺障害申請に真の意味で強いといえるのではないでしょうか。
3 後遺障害申請の方法は被害者請求がオススメ
⑴ 事前認定
相手方加入の任意保険会社に任せることを事前認定といいます。
この方法のメリットは、必要な書類の収集を、保険会社主導でやってくれるため、比較的、被害者本人は楽だという点にあります。
しかし、デメリットとしては、自賠責保険会社に提出する書類の中身を逐一チェックできないため、どのような書類が提出されたか不明であることが多く、場合によっては、後遺障害の等級が認定されにくくなるような意見書が添付されてしまうこともありえます。
⑵ 被害者請求
この方法は、被害者自身、もしくは被害者が委任する弁護士に後遺障害申請を任せる方法です。
メリットとしては、被害者側で、どのような書類にどのような内容が書かれているかを把握したうえで、自賠責に提出するため、安心できるという点にあります(まれに、相手方より、後遺障害認定に関して意見書が自賠責に提出されてしまうこともありますので、被害者に不利な意見書添付を完全に防ぐことができるわけではありません。)。
資料収集は被害者自身で行う場合には、慣れない手続きにとまどうことがあるかもしれませんが、弁護士に依頼すれば、おおむね資料収集の負担も軽減できます。
4 後遺障害申請について注意すべき点
⑴ むちうち
むちうちでも、一定の基準を満たせば(明確な基準が決まっているわけではございません)、後遺障害等級14級9号(場合によっては、12級13号)が認定されることがありますが、適切に後遺障害診断書が記入されていないと、本来認定されるべきであった等級が認定されないという事態が発生しますので、注意が必要です。
例えば、症状が常時痛みやしびれがあるにもかかわらず、後遺障害診断書上では、それが窺えない場合には、等級認定の可能性が本来よりも低くなっている可能性があります。
このような問題がないかを、後遺障害申請に強い弁護士にチェックしてもらう必要があるでしょう。
⑵ 症状や傷病名の記載もれ
複数のケガや症状がある場合に、主治医の先生が後遺障害診断書に全て記入してくれていない場合があります。
なかには、後遺障害等級にあまり関係のない事項もあるため、そのような場合には、問題となりませんが、後遺障害の基準に該当するかもしれない症状が記載されていませんと、自賠責がそれを見落として、正しい後遺障害等級を認定してくれていない事態にもなりかねません。
当法人にご依頼してくださった方の中でも、主治医の先生が、傷病名や症状を書き忘れてしまっていたことは、実際に度々ありましたので、やはり、最終的には、後遺障害申請に強い弁護士にチェックしてもらうのが確実といえます。
5 お気軽にご相談ください
後遺障害申請は、高度かつ専門的知識がなければ、正しく行うことができません。
必ずしも弁護士に頼まなければ、適切な等級が認定されなくなるということではありませんが、まずは、後遺障害申請について、問題が起きていないかを、当法人の交通事故担当弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
大阪にお住まいの方は、ぜひ当法人までご相談ください。
面談相談でも、電話相談でも対応可能です。
腰椎圧迫骨折についての後遺障害申請について
1 後遺障害申請は被害者請求が望ましい

⑴ 後遺障害申請の方法は主に2種類
自賠責保険会社に対する後遺障害等級認定申請の方法には2種類あります。
加害者が加入している任意保険会社経由で申請する事前認定と被害者(又は、その代理人弁護士)が自賠責保険会社に直接申請する被害者請求の方法です。
⑵ 事前認定の考えられるデメリット
事前認定の方法では、病院から任意保険会社へ後遺障害診断書が直接送られることが多く被害者側で後遺障害診断書の内容を確認する機会がないまま手続きが進められてしまうことがあります。
後遺障害診断書に記載されている症状などが実際のものとは異なったものになってしまっている場合、適切な後遺障害等級認定の審査を受けることができません。
例えば、腰椎圧迫骨折の場合には、腰の痛みが残存した場合において、後遺障害診断書に腰の痛みの記載がないときには、痛みに関しては後遺障害の審査がされないことがあります。
そのため、後遺障害診断書には残存している症状が漏れなく記載されていることが重要ですが、事前認定の場合は、漏れがないか否かを確認する機会がなく、そのことは被害者側の大きなデメリットだといえます。
また、被害者に有利な証拠が提出されない可能性が排除できないこともデメリットとして考えられます。
⑶ 腰の痛みの記載について
また、後遺障害診断書に腰椎圧迫骨折に加え、腰の痛みの記載はあるものの適切に症状が記載されていないと適切な評価を受けることができません。
具体的には実際には腰の痛みは常時痛であるにもかかわらず非常時痛であると誤解を招く記載がなされているケースでは、痛みについて適切に後遺障害が認定されないこともあります。
そのため、交通事故被害者の方が適切な審査を受けるためには、被害者側で事前に提出書類を確認できる被害者請求が望ましいです。
提出書類が適切な内容となっているかを確認するには、後遺障害に関する適切な知識が必要になりますので、被害者請求を検討する際には、交通事故に詳しい弁護士に相談することが大切です。
※事前認定の方法では必ず不利になってしまうというわけではございませんので、気になる方は、弁護士までお尋ねください。
2 後遺障害の結果が返ってきた場合
⑴ 結果返却
事前認定であれ、被害者請求であれ、後遺障害の等級が付いた、付かなかった(後遺障害等級非該当)という結果が返ってきます。
通常は、書面で通知がきます。
⑵ 11級7号の認定が件数的に多い
等級認定がされる場合に件数的に多いのは、11級7号「脊柱に変形を残すもの」です。
⑶ 8級相当に昇級するかの検討
この等級(11級7号)が妥当であることも多いのですが、なかには、もうワンランク上の等級である8級相当「せき柱に中程度の変形を残すもの」に該当しうるのではないかというものも一定数あります。
この場合、異議して、11級から8級に昇級するかの見込みを立てるのですが、その際には、実際にレントゲンやCT画像から、胸椎や腰椎の骨の高さ(椎体高)を計測し、前方椎体高の減少が、1個当たりの後方椎体高の50%以上あるかどうかを確認する必要があります。
⑷ 具体的な計測例
| 前方椎体高 | 後方椎体高 | |
|---|---|---|
| 第3胸椎 | 2.14cm | 2.88cm |
| 第4胸椎 | 2.64cm | 3.64cm |
| 第5胸椎 | 3.32cm | 4.26cm |
対象の患者(被害者)の椎体高が上記の通りである場合、
前方椎体高の合計
=2.14+2.64+3.32
=8.1cm…①
後方椎体高の合計
=2.88+3.64+4.26
=10.78cm…②
前方椎体高の減少=②-①=2.68cm…③
1個当たりの後方椎体高
=10.78÷3≒3.59cm…④
1個当たりの後方椎体高の50%
=3.59cm×1/2≒1.8cm…⑤
前方椎体高の減少③(2.68cm)は、
1個当たりの後方椎体高の50%(1.8cm)以上となります。
この被害者の場合は、自賠責(ないし損害保険料率算出機構)に上記のとおり認定してもらえれば、11級から8級に昇級する可能性があります。
3 異議申立てに必要な診断書はどうやって入手するのか
上記のような椎体高の計測は、医師に計測してもらうことになりますが、当法人の場合、顧問の整形外科医と提携しているため、迅速かつ適正な価格で診断書の作成が可能です。
計測の結果、必ずしも、11級7号から8級相当に昇級する基準に該当しているとは限りません。
基準に該当していれば、異議申立てを行っていきます。
4 ご相談は当法人まで
後遺障害申請に詳しい弁護士事務所であるかどうかの判断基準の一つに、実際に後遺障害等級認定機関である損害保険料率算出機構で長年勤務していたスタッフがその弁護士事務所に在籍しているかどうかという基準がありますが、当法人はこの基準を満たします。
他の弁護士事務所が後遺障害申請に詳しいと謳っている場合でも、自称であって、実際にはそこまで詳しくない場合がありますので注意が必要です。
最初から適切妥当な相談を望むのであれば、ぜひ当法人までご相談ください。
大阪、もしくはその近郊にお住まいの方で、来所相談を希望される場合には、大阪の事務所でご相談していただくことが可能です。
お電話でのご相談も受け付けております。
弁護士に依頼した場合の後遺障害慰謝料の違い
1 後遺障害慰謝料について
後遺障害慰謝料は、後遺障害の程度に応じて精神的苦痛を慰謝するものとして支払われる損害項目であり、入院期間や通院期間に対する入通院(傷害)慰謝料とは別に支払われます。
後遺障害の程度は、原則として自賠責保険で認定される後遺障害等級で判断されます。
すなわち、自賠責保険で後遺障害等級が認定された方は、等級の種類に従って入通院(傷害)慰謝料と後遺障害慰謝料の両方とも賠償を受けることになります。
2 自賠責基準と弁護士基準の違い
任意保険会社は、弁護士が介入しない場合に、自賠責基準の金額でしか示談金を提案しないことも少なくありません。
これは、任意保険会社としては、自賠責保険金から支払われる金額で賠償金を済ませることができれば、自社では1円も賠償金を負担せずに済むためです。
そのため、任意保険会社は自賠責保険の範囲内で解決しようとする傾向があります。
ただ、自賠責基準の金額は、裁判基準(弁護士基準ともいいます。)よりもかなり低い金額です。
自賠責保険は、加害者が無資力などの場合に、交通事故被害者の方に最低限の補償を行うという趣旨で設けられた強制保険であるため、裁判基準と比較すると低い支払い基準となっています。
たとえば、後遺障害慰謝料の目安額は、「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」では、1級が2800万円、2級が2370万円、3級が1990万円、4級が1670万円、5級が1400万円、6級が1180万円、7級が1000万円、8級が830万円、9級が690万円、10級が550万円、11級が420万円、12級が290万円、13級が180万円、14級が110万円、が目安になります。
また、「大阪地裁における交通損害賠償の算定基準」では、1級が2800万円、2級が2400万円、3級が2000万円、4級が1700万円、5級が1440万円、6級が1220万円、7級が1030万円、8級が830万円、9級が670万円、10級が530万円、11級が400万円、12級が280万円、13級が180万円、14級が110万円、が目安になります
一方で、「自賠責基準」の後遺障害慰謝料(令和2年4月1日以降発生の事故)は、1級が1650万円または1150万円、2級が1203万円または998万円、3級が861万円、4級が737万円、5級が618万円、6級が512万円、7級が419万円、8級が331万円、9級が249万円、10級が190万円、11級が136万円、12級が94万円、13級が57万円、14級が32万円、です。
このように、裁判基準と自賠責基準では後遺障害慰謝料の目安金額が大きく異なります。
3 後遺障害慰謝料だけでなく逸失利益も要注意
⑴ 裁判基準と自賠責基準との差は大きい
裁判基準と自賠責基準の違いは後遺障害慰謝料だけでなく、逸失利益の金額(数百万円~数千万円、大きい等級ほど、逸失利益の金額が増える傾向にあります。)にも生じます。
⑵ 8級の場合の具体例
ア 自賠責基準 合計830万円
後遺障害慰謝料 331万円
逸失利益 499万円
イ 裁判基準(弁護士基準)の場合 合計5250万0900円
後遺障害慰謝料 830万円
逸失利益 4410万0900円※1
※1 基礎年収:500万円、労働能力喪失率:45%、労働能力喪失期間:30年(ライプニッツ係数19.6004、令和2年4月1日以降の事故に適用されるライプニッツ係数)
ウ 比較検討
上記事例では、裁判基準と自賠責基準の金額は、4000万円以上も違います(被害者側の過失0%の場合)。
弁護士が介入しない場合、任意保険会社は、自賠責保険金程度もしくはそれに少し上乗せした金額程度の賠償案しか提案してこないことが多いです。
つまり、弁護士介入がない場合、数千万円損する可能性があります。
この金額差は、大きい等級が付いているほど、被害者の過失が少ないほど、被害者の年齢が若いほど顕著に表れる傾向にあります。
4 適正な賠償金額の獲得のためのご相談は弁護士法人心まで
適正な賠償金額は、弁護士であれば誰でも獲得できるという簡単なものではありません。
保険会社が、最終回答だといってもきても、そこから交渉をすることで、さらに金額が増額することもあります。
適正な賠償金額を獲得するためには、交通事故に強い、すなわち、交通事故の解決実績が豊富な弁護士に依頼することが大切です。
当法人は、交通事故を集中的に対応するチームを編成し、そこに在籍する弁護士が、交通事故案件を集中的に取り扱って処理していることにより、専門性を高めていますので、交通事故に強い弁護士が多く在籍しています。
大阪にお住まいの方は、電話相談でも可能ですので、お気軽にご相談ください。
後遺障害のご相談のタイミング
1 事故後になるべく早くご相談を!

交通事故に遭ったときは、なるべく早く交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめしています。
とくに、怪我が重い場合は、後遺障害等級認定の申請を行うことも考えながら、適宜必要な検査を受けつつ治療を受ける必要があるため、事故直後から正しい知識を持っていないと間違った方向へ行ってしまうこともあるので要注意です。
2 事故直後から意識しておいた方がよい後遺障害の類型
⑴ むちうち
いわゆるむちうち(頸椎捻挫)の場合は、首の痛みや手の痺れが症状として残ったときに、その症状に後遺障害等級認定を得るためには、通院先、通院頻度、症状の経過症状固定までの期間が重要となってきます。
例えば、仕事が忙しくてなかなか病院に行けないから、それはしょうがないことだと思っていた、保険会社が病院は月1回くらいでいいと言っていた、などという理由で、病院への通院回数が少ない方が少なくないのですが、これでは、本来正しく通院していれば、認定してもらえたはずの後遺障害の等級が認定されない可能性が高くなってしまうおそれがあります。
このようなリスク説明を交通事故に遭ってすぐにしっかり受けていれば、後悔しない選択をすることができます。
後遺障害等級認定の申請を行う段階になってから、知っていたら定期的に病院を受診していたのにと後悔をしても取り返しがつきませんので、交通事故に遭った時点で正しい知識を得ておくことが重要です。
⑵ 高次脳機能障害
交通事故で、頭をケガして、脳挫傷やびまん性軸索損傷を負ったり、意識を失ったりした場合などで、高次脳機能障害が残る可能性がある場合にも、事故直後から意識しておいた方がいいことがあります。
高次脳機能障害は争いになることも多い障害ですので、詳細は、実際に弁護士までご確認ください。
3 お気軽にご相談ください
「特にもめているわけではないので、弁護士に相談する必要はないのではないか」「弁護士に相談するのはまだ早いのではないか」「ほかの弁護士事務所では、通院が終わってからまた相談してくださいと言われた」などという理由で、相談するのを躊躇される必要はございません。
上記のとおり、正しい知識を早期に得ておくメリットは大きいです。
一度、ご相談してくだされば、現時点でのアドバイスをさせていただきますし、相談したイコール契約しなければならないわけでもありませんのでご安心ください。
4 通院終了後では手遅れになっている場合も・・・
治療費用の支払いが打ち切られてからでは、打ち切りの延長交渉が成功することはかなり難しいと思ってください。
また、むちうちの方は、打ち切られてから、通院継続をしていないと、初回の後遺障害申請で等級が認定されずに等級非該当の結果がでてしまった場合に、2回目の申請である異議申し立てをしても、通院にブランクがあるということで、再び等級が認定されないという事態にもなりかねませんので、注意が必要です。
間違った方向に行かないためにも、軌道修正をするためにも、なるべく早いタイミングでのご相談が望ましいといえます。
5 等級認定された後でも遅くありません
弁護士に相談した方がいいということは、皆様いろいろなタイミングで知ることになると思います。
相談のタイミングは早い方が良いですが、どのようなタイミングでも相談する価値がないほど遅すぎるということはありません。
各タイミングでご相談いただくメリットはあります。
例えば、後遺障害申請をして、等級認定結果が出たあとに、弁護士に相談するという手段があることを知る場合もあると思います。
そのような場合でも、もし等級が認定されなかったり、実際の症状からして低く認定されてしまったりしているような場合には、異議申立て等をするという方法があります。
ですので、等級が認定された後でも、もう手遅れではないのかとあきらめることなく、すぐに弁護士までご相談ください。
仮に、等級が覆せなかったとしても、ご本人様で示談交渉するよりかは、弁護士を介入させた方が、損害賠償金が多くなる可能性が高くなります。
症状固定日について
1 症状固定と症状固定日
⑴ どの日を症状固定日とするかについて
交通事故で怪我を負ったとき、その怪我の症状は、治療により徐々に改善していき、ある一定の時期以降は治療を受けてもその効果が期待できなくなり改善が見込まれない状態になるという経過を一般的にたどります。
そして、治療を続けても症状の改善が見込まれない状態を症状固定いい、症状の改善が見込まれない状態に達した日を症状固定日といいます。
症状固定か否かの判断は、怪我の症状の経過をみたときに、以前の状態と比較していつまで症状の改善が見込めたかで判断されます。
そのため、ある日を境として急に症状固定に至るということは考え難く、症状固定に至っているかについて見極めるため一定の期間を要することが多いです。
⑵ 誰が症状固定日を判断するのか
症状固定日について、被疑者側と加害者側で見解が異なる場合、誰がどのように判断するのか疑問に思われることと思います。
この点、症状固定日の判断については、基本的に医師の判断が尊重され、後遺障害診断書に医師が記載した症状固定日をもって症状固定日と判断されることが多いです。
ただ、症状固定とは、医学的な用語ではありませんので、当事者間の話し合いで症状固定日が決まらない場合は、最終的には裁判所の裁判官が症状固定日を判断します。
そのため、事故状況、症状の経過などを考慮して、裁判所が医師の判断と異なる症状固定日を認定することもあります。
2 症状固定日が問題となる理由
症状固定日について争いとなる理由は、加害者の賠償責任の範囲が関係してくることにあります。
交通事故の加害者は、原則として症状固定日までの治療費を負担すれば足ります。
症状固定日よりも後の治療費は負担する義務を負いません。
受けたとしても何ら治療効果をもたらさない治療等に係る費用については加害者が負担する必要がないというのが賠償上の考えであるためです。
また、入通院慰謝料についても、事故発生日から症状固定日までの期間を前提に算定されるため、より手前の日が症状固定日であるとされた方が、加害者にとって賠償上有利となります。
3 被害者として留意すべきこと
症状固定の判断に際しては、症状の改善の推移が把握できることが前提となります。
頸椎捻挫などのように、治療経過に関する客観的な証拠が乏しい症例については、ご自身の症状について正確に医師に伝え、これをカルテ(医療記録)に記載してもらうことが、症状固定日を正確に把握するために必要となります。
ただ漫然と診察を受け続けるのではなく、ご自身の状態を、医師に伝え記録に残してもらうように心がけてください。
4 保険会社からの症状固定の案内に注意
実際には主治医が症状固定と判断していない場合であっても、保険会社から、「症状固定なので治療費を打ち切ります」「症状固定に至っていると思いますので、後遺障害診断書を主治医の先生に記載してもらってください」などと言われることがあります。
保険会社が治療費を早期に打ち切ることを目的として、まだ症状固定に至っていないにも関わらず、症状固定という概念を持ち出していることもありますので、治療費の打ち切りや後遺障害申請について案内があった場合には、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
5 後遺障害申請は弁護士にお任せください
治療を継続したものの症状が残ったまま症状固定に至ってしまった場合には、それ以降の治療費の賠償が受けられなくなりますので、残った症状について、加害者側から賠償を受けるために後遺障害申請を考えられる方も多いです。
自賠責保険会社に対する後遺障害等級認定申請は、認定基準の重要な部分が非公開となっており、弁護士であってもその認定基準の重要な部分は知らないことが多いです。
当法人では、後遺障害等級認定申請の審査機関である損害保険料率算出機構の元職員が在籍しており、後遺障害の認定基準や運用について精通していることを強みとしています。
症状固定時に残っている症状について後遺障害申請を検討されている方は、弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください。
本当に交通事故に詳しい弁護士の見分け方
1 どのような弁護士に依頼するべきか

後遺障害について相談するとき、せっかく相談するなら交通事故に詳しい弁護士にお願いしたいと思われる方は多いかと思います。
しかし、何を基準に詳しいかどうかを判断すればよいか判らない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
後遺障害に詳しい弁護士探す際の主なポイントとしては、以下のような点が挙げられます。
- ・解決実績が豊富
- ・勉強会などの社内体制が整っている
- ・認定機関に在籍していたスタッフがいるか
以下では、それぞれのポイントについてご説明いたします。
2 解決実績が豊富な事務所であるかどうか
⑴ 自称の可能性
「交通事故に強い」と謳っている事務所は、数多くあります。
しかし、それは「自称」にすぎない場合もあるかもしれません。
飲食店が、「うまい〇〇」「おいしい〇〇」と宣伝文句的に書いているのと同じことです。
⑵ 解決実績は信用性の高い指標
その中で、交通事故の解決実績を掲載している事務所は、信用性が高いといえます。
掲載している解決実績が虚偽であれば、詐欺罪等の犯罪に該当する可能性があるため、事務所ぐるみで虚偽の解決実績を載せるリスクを冒す事務所はないと考えられるからです。
当法人が掲載している解決実績も、個人が特定されないように、多少抽象化して記載していますが、全て当法人所属の弁護士が、被害者の方の満足度を追求し、保険会社と強気に交渉していった結果、得られたものです。
3 指導体制や勉強会がしっかりしているかどうか
⑴ 交通事故を得意とする弁護士の指導体制が存在しているか
交通事故の解決実績が豊富な事務所であっても、そこに所属しているすべての弁護士が一律に交通事故を得意としているとはいいきれない場合も当然にあります。
例えば、その事務所での経験年数が長くても、今まで交通事故案件は多く扱ってこなかったという弁護士は、交通事故に強いといえるかは疑問です。
当法人には、新人弁護士もおりますが、交通事故に不慣れな弁護士がいきなり交通事故の案件を一人で担当するようなことはなく、交通事故の取り扱い件数が豊富な指導担当弁護士と共同で事件処理に当たっているため、ご心配無用です。
また、たとえ弁護士経験年数が少なかったとしても、これまで処理してきた交通事故事件の数という点においては、集中的に交通事故を取り扱っていることから弁護士経験年数が長い弁護士よりも勝っている場合もあり、その分経験やノウハウを蓄積しているといえます。
⑵ 勉強会の開催
交通事故の賠償実務は、法改正などもあり、常に動いています。
今までの常識が時代の流れとともにずれていくこともあります。
また、専門的な知識については、インプットしていく必要もあります。
弁護士であっても、常に自己研鑽を積んでいなければ、依頼者の方に満足いただける解決は難しいと考えられます。
この点、当法人の交通事故担当弁護士は、定期的に、交通事故についての勉強会の開催や、知識のインプット、ブラッシュアップをしており、各弁護士が日々自己研鑽に努めています。
4 認定機関に在籍していたスタッフ
後遺障害に詳しい事務所の見分け方として、その事務所に実際に後遺障害の等級認定機関(自賠責調査事務所、損害保険料率算出機構)に在籍していたスタッフがいるかどうか、という点も重要なポイントです。
後遺障害の等級認定機関に在籍していたスタッフと連携することで、弁護士は、より詳細な後遺障害認定の実務の知識を得ることができます。
上記のような環境にない事務所でも、弁護士自身が経験されて、後遺障害に詳しくなられた方も少なからずいらっしゃると思いますが、中には、見ようみまねで後遺障害申請をしているだけの弁護士もいるかもしれませんので注意が必要です。
5 当法人にご相談ください
弁護士法人心 大阪法律事務所では、ホームページにも掲載しているとおり交通事故や後遺障害の申請に関する案件を多く取り扱っております。
まずは、相談だけと考えている方も、お気軽にご相談ください。
交通事故を多く扱っている弁護士が相談に乗らせていただきます。