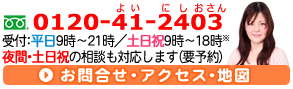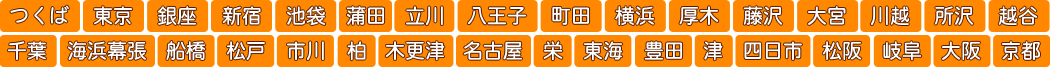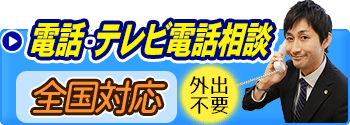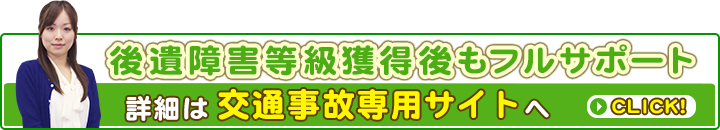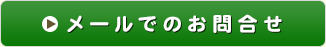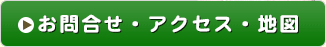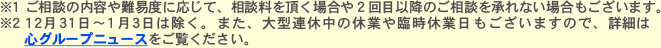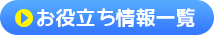岐阜で後遺障害で弁護士をお探しの方へ

1 岐阜の方は当法人にご相談ください
弁護士法人心 岐阜法律事務所は、岐阜駅から徒歩3分、名鉄岐阜駅から徒歩2分の場所にありますので、お近くにお住まい・お勤めの方にとってご利用いただきやすいかと思います。
調整の上、土日祝日や平日夜間のご相談もしていただけますので、お仕事等のご事情で事務所に行く時間が作りづらいという方もご安心ください。
後遺障害は電話・テレビ電話相談に対応しておりますので、来所が難しいという方にも気軽に相談していただけるかと思います。
電話相談をご利用の場合は、電話、メール、郵送等を使ってご相談からご依頼まで対応させていただきます。
ご相談のお申込みはお電話やメールフォームから承っておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
2 後遺障害の案件を得意とする弁護士をお選びください
交通事故によって障害がお身体に残ってしまった場合、後遺障害等級申請や相手方との示談交渉など、行うべきことが数多くあります。
また、これらの手続きを適切に行うためには、法的な知識や後遺障害に関する医学的な知識が必要となりますので、弁護士にご依頼される際は、後遺障害の案件を得意としている弁護士をお選びになることをおすすめいたします。
当法人は、後遺障害案件に力を入れて取り組んでいます。
損害保険料率算出機構の元職員や損害保険会社の元代理人弁護士がいる強みを活かし、情報交換を行ったり、内部研修を開催したりして、日々研鑽を積んでいます。
難易度の高い後遺障害案件にも対応することができますので、安心して当法人にお任せください。
3 無料診断サービスもご利用いただけます
いきなり弁護士事務所にいくのは不安だという方や、まずは自分がどれくらいの後遺障害等級の認定を受けられそうなのか知りたいという方のために、当法人は「後遺障害認定無料診断サービス」を実施しております。
これは、相談者の方のお話やカルテなどをもとに、妥当な後遺障害の等級を弁護士が予測するサービスです。
どれくらいの等級が適正か分からず不安を感じていらっしゃる方などは、お気軽にこちらのサービスをご利用ください。
無料診断サービスをご希望の方も、まずはフリーダイヤルやメールフォームにてお問い合わせください。
後遺障害の申請をする際に気を付けること
1 適切な等級認定を獲得するために気を付けるべきこと

交通事故で負った傷害について治療によっても症状が残ってしまった場合には、後遺障害の申請をすることができます。
しかし、症状が残ればただちに等級認定されるわけではありません。
適切に症状を伝え、認定基準に照らし後遺障害が認められるべきことをしっかりと示していかなければなりません。
そのために申請で気を付けるべきことをご説明します。
2 症状固定時期か否か見極めること
まず、後遺障害を申請すべき時期にあるか見極めることが大切です。
治療によっても症状の改善が見込まれなければ症状固定となり、後遺障害の申請をすべき時期が到来したといえます。
保険会社による治療費対応が打ち切られた時期が必ずしも症状固定時期であるとは限りません。
3 等級認定に必要な検査を受けること
後遺障害の認定では必要な検査を受けておかなければならない場合があります。
例えば、耳鳴りについての後遺障害等級認定では、ピッチマッチ検査とラウドネスバランス検査の結果を確認するため、これら検査を受けていなければ等級認定されません。
したがって、ご自身の症状において等級認定の審査で必要な検査があるか、また、その検査を受けているか、注意が必要です。
4 診断書に症状等が適切に記載されていること
後遺障害の審査では、とりわけ主治医が作成する後遺障害診断書の内容が重要です。
もっとも、主治医は被害者の症状を常に見ているわけではありません。
被害者側から主治医に対して症状をしっかりと伝えて、後遺障害診断書に適切に反映してもらうことが大切です。
5 被害者請求によること
後遺障害の申請方法には、被害者側で申請する「被害者請求」という方法と、任意保険会社側で申請する「事前認定」の方法があります。
任意保険会社は認定結果に応じて支払う立場であるため、認定に有利な資料収集を十分に行うとは限りません。
「被害者請求」の方法であれば、資料収取などを十分に行い、万全な状態で申請することができるため、適切な等級認定を獲得するためには、被害者請求の方法によるべきです。
6 弁護士へのご相談
先ほど述べた、症状固定時期の見極め、必要な検査の確認、後遺障害診断書に症状が適切に反映されるための主治医への症状の伝えることなど、個別の事案において対応しなければならないことは多々ありますので、交通事故に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。
当法人では、弁護士や損害保険料率算出機構の元職員等で構成される後遺障害チームが後遺障害申請手続をしっかりとサポートしております。
後遺障害申請をお考えの場合には、お気軽に当法人にご連絡ください。
後遺障害逸失利益とは
1 後遺障害逸失利益とは

交通事故で後遺障害が残ると、労働能力の減退が生じ、将来の収入が減少すると考えられています。
この将来の収入減を後遺障害逸失利益といいます。
後遺障害逸失利益は、「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」の計算式で算出します。
具体的内容についてご説明します。
2 基礎収入について
基礎収入は、原則として、事故前の現実収入を参考とします。
なぜなら、後遺障害がなければ、将来においても現実収入程度の収入を得られるだろうと考えられるからです。
給与所得者である場合には事故前年度の源泉徴収票を、個人事業主である場合には事故前年度の確定申告書類を参考に基礎収入を算出するのが一般的です。
また、同居の家族のために家事労働を行い、家事従事者として認められる場合には、女性全年齢平均賃金センサスを参考に基礎収入を算出することが多いです。
3 労働能力喪失率について
労働能力が減退する割合のことです。
実務では「後遺障害別等級表・労働能力喪失率」が参考にされており、等級の程度により異なる喪失率が定められています。
具体的には、後遺障害等級1級~3級は労働能力喪失率が0%、4級92%、5級79%、6級67%、7級56%、8級45%、9級35%、10級27%、11級20%、12級14%、13級9%、14級5%と定められています。
もちろん、これらは参考であるため、職業や後遺障害の内容等によっては目安を上回る喪失率が認められることもあります。
例えば、ピアニストに手指の機能障害がある場合、その後遺障害は職業に直結するものであり、将来の収入面への支障は通常よりも大きいといえるから、目安を上回る喪失率が認められることもあると思います。
4 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数について
原則として67歳までとし、67歳を超えている場合には平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とします。
この点も、職種、地位、健康状態等を踏まえ、事案により原則と異なる認定がされることがあります。
なお、神経症状の後遺障害の場合には永続するものでないとして、14級なら5年程度、12級なら10年程度と制限されることも少なくありません。
また、将来の長期間にわたって発生する収入減を一時金として受領する場合、中間利息を控除する必要があります。
そのため、労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数をかけます。
5 弁護士法人心にご相談ください
後遺障害逸失利益について適切な金額を獲得するには、労働能力喪失率や労働能力喪失期間について、具体的事情を踏まえて主張立証することはもちろん、まずは、適切な等級認定を獲得しなければなりません。
後遺障害等級認定の獲得では、経験に基づく豊富なノウハウが必要です。
当法人では、数多くの後遺障害事案を取り扱ってきた実績がありますので、後遺障害の申請をお考えの場合や、後遺障害の補償についてお悩みの場合には、お気軽に弁護士法人心 岐阜法律事務所までご連絡ください。
後遺障害について相談するタイミング
1 できるだけ早期の相談が望ましい

事故直後はとにかく症状が辛いことから、一日も早く治りたいという思いが強く、後遺障害のことは考えていらっしゃらない方も多いかもしれません。
もちろん、治ることが一番ですので、しっかり治療を受けることが大切であることは当然ですが、万が一、後遺障害が残った時に症状を証明する証拠が足りないことや受けるべき検査を受けていないために後遺障害が認定されないことを防ぐことも大切です。
たとえば、むちうち症で症状が残ってしまったにもかかわらず、適切な頻度で通院していなかったがために後遺障害が認定されないことなどが生じることがあります。
万が一に備えて、できるだけ早期に後遺障害に詳しい弁護士からアドバイスを受けておくことが大切です。
2 遅くとも後遺障害申請前に相談
後遺障害申請は書面審査が中心で、主に画像所見や診断書などの医療記録の内容によって認定の可否や等級が判断されます。
そのため、実際の症状と異なる内容が後遺障害診断書などに記載されていても、それを前提にして、本来後遺障害が認定されるべき方が認定されないこともあります。
どのような記載が後遺障害認定において不利になるのか、または、有利になるのかを事前に確認しておけば、有利な事情が漏れているのであれば、それを補完することができることもあります。
また、不利な記載がされている場合であっても、その他の事情を補完することで、誤解なく症状が伝わるようにできる場合もあります。
後遺障害申請後では手遅れになることも多いため、遅くとも後遺障害申請前には、後遺障害に詳しい弁護士からアドバイスを受けておくことが大切です。
3 後遺障害申請の結果が出た後であっても相談した方が良い
本来、後遺障害が認定されるべきであるにもかかわらず、認定されていないことや本来得られるべき等級が認定されていないことがあります。
この場合に、適切な証拠を集めて異議申立手続をとることにより、後遺障害等級が変わることがあります。
後遺障害申請の結果が出た場合には、後遺障害に詳しい弁護士からアドバイスを受けておくことが大切です。
後遺症が複数残ったときの後遺障害等級
1 後遺症が複数ある場合の等級認定

後遺症が残った場合、後遺障害等級認定がなされることがあります。
後遺症が複数ある場合にもそれぞれについて等級認定されますが、最終的には、「併合」というルールにより一つの等級認定がなされることがあります。
以下、併合のルールと、その例外をいくつかご紹介します。
2 併合のルール
⑴ 5級以上の等級に該当する後遺障害が2つ以上→重い方の等級を3級繰り上げ
⑵ 8級以上の等級に該当する後遺障害が2つ以上→重い方の等級を2級繰り上げ
⑶ 13級以上の等級に該当する後遺障害が2つ以上→重い方の等級を1級繰り上げ
⑷ 14級に該当する後遺障害が2つ以上→14級のまま
3 併合のルールの例外
⑴ 等級を繰り上げると序列を乱す場合
上肢を手関節以上で失うと5級の4となり、他方の上肢をひじ関節以上で失うと4級の4に該当するため、併合のルールを適用すると、重い方の4級を3級繰り上げて1級になるように思われます。
しかし、1級の3には「両上肢をひじ関節以上で失ったもの」という等級があり、この程度に達しないため、併合2級にとどまります。
⑵ 併合すると1級を超える場合
2級に該当する後遺障害と、3級に該当する後遺障害がある場合、重い方の2級を3級繰り上げると1級を超えてしまいます。
しかし、1級以上の等級はないため、併合1級になります。
⑶ 一つの障害が2つ以上の等級に該当すると考えられる場合
大腿骨に変形を残して12級の5となり、その結果、その下肢を1センチメートル短縮して13級の8となる場合、重い方の12級を1級繰り上げることにはなりません。
この場合、重い方の等級である12級の5の等級とします。
⑷ 1つの障害に他の障害が通常派生する関係にある場合
右上肢に偽関節を残して8級の8になるとともに、その箇所に頑固な神経症状を残して12級の13になる場合、重い方の8級を1級繰り上げることにはなりません。
この場合、重い方の8級の8の等級とします。
4 弁護士にご相談ください
後遺障害の等級認定の考え方は複雑であり、一般の方が正確に理解することは容易ではありません。
後遺障害の等級認定に関してお悩みの場合には、お気軽に弁護士法人心 岐阜事務所にご連絡ください。
後遺障害における成年後見制度について
1 成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が欠く方を保護するための制度です。
申立てによって、家庭裁判所が、本人を援助する「成年後見人」を選任します。
成年後見人は、本人に代わって契約を締結したり、本人の契約を取り消したりすることができますし、また、本人のために財産全体を管理したりします。
2 後遺障害の内容・程度によって成年後見制度が必要となる
交通事故の受傷により後遺障害が残ることがあります。
とりわけ重度の後遺障害では、成年後見制度の利用が必要になることがあります。
例えば、脳挫傷により高次脳機能障害となり、寝たきりの要介護状態となる場合には、通常、後遺障害等級について別表1の第1級または第2級の等級に該当します。
このような場合には、本人に判断能力が欠くことが多く、その場合、本人のために成年後見人を選任する必要があります。
判断能力を欠く状態では有効な法律行為と認められず、示談などをすることができないからです。
成年後見人を選任しないと事件の解決を図ることができませんし、仮に、そのような状態で示談したとなると、後に示談の有効性を争われてしまう可能性もあります。
3 成年後見人をつけるべきか否か判断が難しい場合
判断能力を欠くことが明らかである場合もあれば、判断能力を欠くといえるか判断が難しいケースもあります。
この点、成年後見人の申立資料には、医師が作成する診断書や福祉関係者が作成する書類があり、それらに記載される、本人の日常・社会生活の状況や判断能力についての意見を踏まえて、裁判所が後見開始の審判をするか否か判断します。
したがいまして、本人が判断能力を欠くと評価できるか判断が難しい場合には、医師や福祉関係者に対して意見を聞くなどして、方針を決めることになります。
その他、成年後見人選任の手続を進めるにあたっては、成年後見人の候補者をどうするかなど事前に検討すべき点がありますので、交通事故で成年後見人の選任が問題となる場合には、早めに、交通事故に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
4 弁護士法人心 岐阜法律事務所にご相談ください
弁護士法人心では、後遺障害の等級認定の獲得にこだわり、これまで徹底して取り組んできました。
重度の後遺障害の等級認定を獲得した実績も多数あり、判断能力が欠く場合には、成年後見人選任の申し立ての手続きもサポートしております。
重度の後遺障害が残るかもしれない、成年後見人選任の申立てはどのようにしたらよいかなど、お困りのことがあれば、お気軽に弁護士法人心 岐阜法律事務所までご相談ください。
後遺障害認定の結果に不服がある場合はどうすればよいか
1 不服がある場合の対応

後遺障害の等級認定の申請をしたものの、認定結果に不服がある場合、異議申立て、紛争処理機構への申し立て、及び訴訟提起の3つの方法が考えられます。
以下、順に手続きの内容について説明します。
2 異議申立てについて
異議申立ては、自賠責保険会社に対して行います。
認定結果について再考を求める手続です。
費用の負担なく、回数に制限なく何度でも行うことができます。
初回申請時と同じ資料を添付しても結果が変わらないことが多いため、異議申立てをする際には、新たな資料を添付することが一般的です。
3 紛争処理機構への申し立てについて
紛争処理機構は、自賠責保険の判断内容の妥当性を審査します。
審査は、弁護士、医師及び学識経験者で構成する紛争処理委員が合議制で行います。
すでになされた自賠責保険の判断内容を審査するものであるため、新しい証拠を提出することはできません。
新しい証拠の提出を予定している場合には、異議申立てを選択しましょう。
また、紛争処理機構への申し立ては無料ですが、1度しかできません。
そのため、異議申立てでは功を奏しない場合に紛争処理機構への申し立てをするのが一般的です。
4 裁判について
裁判所に訴状を提出し、中立公正な裁判官に判断してもらう手続です。
異議申立てや紛争処理機構への申し立てが書面審査であるのに対し、裁判は書面審理でないため、十分な審理が期待できます。
他方で、1年以上要することもあるなど事案解決まで長時間要します。
また、裁判費用の負担もあります。
5 後遺障害認定結果に不服がある場合には弁護士にご相談ください
個別の事案ごとに、不服申し立ての見込みの程度、新しい証拠の有無、手続に要する時間などを総合的に考慮して、適切な方法を選択しなければなりません。
弁護士法人心 岐阜法律事務所では、数多くの後遺障害案件を通じて培った膨大なノウハウに基づき、事案に応じた適切な方法を提案いたします。
後遺障害の認定結果に不服がある場合には、弁護士法人心岐阜法律事務所にご連絡ください。
後遺障害と症状固定との関係について
1 後遺障害と症状固定との関係

治療を行っても、完全に治らずに身体や精神に障害が残ることがあり、治療による効果が期待しえない状態を「症状固定」といいます。
症状固定時に残った症状については、賠償の対象となる「後遺障害」に該当するか問題となり、後遺障害の等級認定獲得に向けて、自賠責保険に申請することができます。
このように、手続き上、症状固定は後遺障害の前提となります。
これにとどまらず、症状固定は、後遺障害について適切な等級認定や損害賠償を獲得するために重要な意味を持つため、以下、ご説明します。
2 適切な等級認定獲得との関係
症状固定日は治療による効果が期待しえない時期であるから、その判断では当然ながら医学的判断が重要です。
したがって、症状固定時期の判断では、主治医の診断内容が原則として尊重されます。
しかし、実務上、任意保険会社が、主治医の見解と関係なく、症状固定とするよう働きかけてくることが少なくありません。
治療効果が期待できる状態であるにもかかわらず、症状固定としてしまうと、症状固定後も症状改善の見込みがあるとして、等級認定を否定する理由にもなりえます。
したがって、適切な等級認定を獲得するためには、任意保険会社の言われるままに症状固定にするのでなく、主治医の見解やご自身の症状の推移等を踏まえて、慎重に判断しなければなりません。
3 適切な損害賠償獲得との関係
後遺障害についての損害としては、後遺障害慰謝料、逸失利益(後遺障害による将来の減収)、将来介護費、将来装具費等があります。
これらの損害費目は、後遺障害の等級の内容や程度等によって、大きく変わるため、適切な等級認定を獲得できなければ、損害賠償額はかなり少なくなります。
例えば、将来介護費では、要介護状態であることが必要であるため、重度の等級認定を獲得できなければ全く認められない可能性がありますし、また、将来装具費は、対象となる患部について等級認定がなされなければ、通常、その損害賠償が認められません。
したがって、症状固定時期の判断は、適切な等級認定の獲得だけでなく、その後の適切な損害賠償にも大きく影響を及ぼします。
4 症状固定日判断のポイント
症状固定日は、医師の判断、症状の推移、治療内容、治療結果、検査結果などを踏まえて判断されます。
したがって、被害者の方は、症状があれば通院を継続すること、日頃から医師に対して症状をしっかり伝えてカルテ等に残してもらうこと、症状に応じた必要な検査を受けておくことなど、受傷初期から気を付けておくべきポイントはたくさんあります。
具体的にどのような点にどのように対応すべきか事案ごとに異なりますので、交通事故に遭われた場合には、できるかぎり早期に交通事故に精通した弁護士に相談し、アドバイスをいただくようにしましょう。
5 弁護士法人心にご相談ください
弁護士法人心は、後遺障害チームを作り、適切な等級認定の獲得に徹底的にこだわり、受傷初期から交通事故のサポートも行っております。
交通事故の相談料は原則無料で対応しておりますので、まずは、交通事故に遭われた際には、お気軽に弁護士法人心岐阜法律事務所までご連絡ください。
後遺障害を申請する際の流れ
1 症状固定時期にあること

後遺障害の申請では、治療効果がこれ以上見込まれない時期に至ったとき、そのときに残った症状が審査対象となります。
治療効果が見込まれる場合には、未だ症状固定の時期にあるとはいえず、後遺障害の申請をすべきタイミングではありません。
症状固定時期にあるか否かは、原則として、担当医の見解が尊重されます。
2 申請方法の選択
症状固定時期に至った場合、次に、後遺障害の申請方法を選択します。
申請方法には、保険会社が申請手続を行う「事前認定」という方法と、被害者側で申請手続を行う「被害者請求」という方法があります。
事前認定の方法は手間がかからないというメリットがありますが、有利な資料を積極的に収集・提出するとは考えにくいというデメリットがあるため、原則として、被害者請求の方法によるべきです。
3 後遺障害診断書の作成依頼
担当医に後遺障害診断書の作成を依頼します。
経験上、3週間程度で作成されることが多いように思われます。
後遺障害診断書の内容は審査において極めて重要であるため、症状が適切に反映されるよう作成してもらうことが大切です。
4 その他資料の収集
被害者請求では、①後遺障害診断書のほか、②支払請求書兼支払指図書、③交通事故証明書、④事故発生状況報告書、⑤診断書及び⑥診療報酬明細書などの書類が必要です。
任意保険会社が治療費の対応をしている場合、通常、任意保険会社から③、⑤、⑥の書類のコピー(原本証明印付)を取り付けることができます。
そのほか、必要に応じて、医師の意見書や職場の陳述書などを取り付けます。
5 自賠責保険会社に請求資料を提出
被害者請求では、資料が揃ったら、事故の相手方の自賠責保険会社に対して請求書類一式を送付します。
自賠責保険会社は、後遺障害認定機関である損害保険料率算出機構に資料を送付し、そちらで等級認定についての審査が行われます。
6 認定結果
事案にもよりますが、申請書類一式を提出してから、3、4か月程度で認定結果の通知が届きます。
等級認定された場合には、等級の内容等に応じて、自賠責保険金が支払われます。
例えば、後遺障害14級9号の等級認定がなされた場合、75万円を上限とする自賠責保険金が支払われます。
7 不服の申し立て
認定結果に不服がある場合、異議申立て、紛争処理機構への申請及び訴訟提起などの方法をとることができます。
8 後遺障害の申請は当法人にお任せください
適切な等級認定を獲得するには、被害者請求の方法によるべきですが、認定上有利な資料にどのようなものがあるか考えて行動に移すのはノウハウが必要です。
そのため、一般の方が行うのは容易ではありません。
当法人は、後遺障害チームを作り、適切な等級認定の獲得に徹底的にこだわり、取り組んでおります。
後遺障害の申請をお考えの場合には、お気軽に当法人までご連絡ください。
後遺障害と将来介護費の請求
1 後遺障害が残った場合に将来介護費を請求できる場合がある

交通事故によって後遺障害が残った場合、将来的に介護を要する場合があります。
例えば、脳を損傷して後遺症が残って寝たきりになった場合が考えられます。
このように、残った後遺障害の内容や程度によっては、将来的に介護が必要となるから、将来的に要するだろう介護費用を加害者に請求することができます。
2 将来介護費が認められる場合
介護の必要性すなわち後遺障害によって介護を要する状態であることが必要です。
後遺障害等級別表第1の1級と2級は、介護を要する状態にあることが後遺障害の要件であるため、通常、これら等級が認定されれば介護の必要性がただちに認められます。
これに対して、後遺障害等級別表2の3級以下の等級が認定された場合、介護を要する状態にあることが要件になっていないため、ただちに介護の必要性は認められるということはありません。
ただし、3級以下であっても、医師から介護の指示があったり、家族の見守りや声かけなど介護が必要といえる場合には、介護の必要性が認められることがあります。
3 将来介護費の1日あたりの目安額
職業付添人、たとえば、看護師やヘルパーの訪問介護による場合には実費となります。
裁判例では、日額1万8000円から2万程度を認めるケースも珍しくありません。
これに対し、ご家族など近親者による介護の場合、1日あたり8000円程度を目安とされることが多いです。
ただし、介護の内容や程度等によって1日あたりの金額は増減します。
例えば、見守り・声かけの介護のみである場合、日常生活動作の介護まで行う場合よりも負担が小さいといえるため、1日あたりの金額も小さくなります。
4 将来介護費の算定方法における注意点
将来介護費は、「日額×365×介護の期間の年数に対応するライプニッツ係数」の計算式にあてはめて算定します。
将来介護費では、介護の必要性の有無や、こちらが主張する介護の内容・程度の相当性について、争われることが少なくありません。
そのため、後遺障害の等級認定資料、カルテ等の医療記録、介護の実情を知る人からの聴き取りなどから、被害者の生活の実態や実際の介護の内容などを正確に把握した上で算定を行う必要があります。
5 交通事故に精通する弁護士にご相談ください
将来介護費は金額が大きくなるため、保険会社は多くの事案で争ってきます。
適切な将来介護費を獲得するには、生活の実態や実際の介護の内容などの把握と、それを裏付ける証拠の収集を十分に行う必要があります。
当法人では、交通事故を集中的に取り扱う「交通事故チーム」を作り、将来介護費が問題となる重傷案件を数多く取り扱ってきました。
将来介護が必要になるような重症を負った場合には、まずは弁護士法人心 岐阜法律事務所までご連絡ください。
後遺障害の2つの申請方法
1 後遺障害申請の申請方法について

後遺障害の申請方法には、「事前認定」と「被害者請求」の2つがあります。
それぞれの手続きの概要やメリット・デメリットについて、以下、ご説明します。
2 事前認定について
⑴ 手続きの概要
任意保険会社は、自賠責保険を超える分について賠償対応をすればよいのですが、任意保険会社が最初から自賠責保険を超える分のみならず、自賠責保険分についても一括して対応して支払いをすることがあります。
任意保険会社は、後で自賠責部分を自賠責保険から回収するため、被害者への支払いに先立ち、自賠責保険の損害調査を行う損害料率算出機構に対し、後遺障害等級の有無の判断について事前に確認を行います。
この事前の確認手続が「事前認定」です。
⑵ メリット・デメリット
事前認定は、任意保険会社が行う手続きであるから、資料の収集・提出のほとんどを任意保険会社が行います。
したがって、被害者の手間は少ないです。
その反面、被害者は、資料の収集・提出にほとんど関与しないため、不備なく資料の取り付けができているか、取り付けた資料に症状が適切に反映しているか、十分に検証できません。
また、事前認定で後遺障害等級の認定が明らかになったとしても、保険金の支払いはなく、示談等で解決するまでお金が入ってきません。
後述の被害者請求よりも手元にお金が入るタイミングは遅いです。
3 被害者請求について
⑴ 手続きの概要
被害者側が自賠責保険会社に対して、後遺障害等級認定の判断を求める手続きです。
⑵ メリット・デメリット
被害者請求は、被害者側が行う手続きであるから、資料の収集・提出の多くを被害者側で行います。
したがって、事前認定と比較して、手間がかかります。
他方、取り付けるべき資料を不備なく取り付けているか、診断書等に症状が適切に反映されているか、など十分に検証可能であること、また、不十分であれば追加で取り付けるといったこともできます。
また、被害者請求で等級認定されると、自賠責保険から等級に応じて保険金が支払われます。
4 どちらの申請方法によるべきか
適切な等級認定を獲得するには被害者請求によるべきです。
等級認定は原則として書面審査であるため、いかに申請前に有利な資料を収集できるかが重要であるからです。
確かに、資料収集・提出で手間がかかりますが、弁護士に依頼することでその手前を最小限に抑えることができます。
当法人では、後遺障害チームを作り、数多くの事案で適切な等級認定を獲得してきました。
後遺障害申請を少しでもお考えの場合には、まずは弁護士法人心 岐阜駅法律事務所までご連絡ください。
後遺障害申請について弁護士に依頼するメリット
1 適切な等級認定を獲得することの重要性

後遺障害申請でどのような等級認定がなされたかによって、損害賠償額が大きく異なりますので、保険会社任せにすべきではありません。
適切な等級を獲得するためには交通事故に精通した弁護士に後遺障害申請を依頼されるべきです。
弁護士に依頼する具体的メリットは、以下のとおりです。
2 様々なアドバイスを受けることができる
後遺障害の審査は、認定基準に基づき行われるため、認定基準に対する正確な理解が求められます。
弁護士に依頼した場合、適切な病院選び、受けるべき検査、通院における注意点など、等級認定に関わる重要なポイントについて、幅広くアドバイスを受けることができます。
仮に、等級認定基準に照らし必要とされる検査を受けなかった場合、いくら症状が重かったとしても、非該当の判断がされることがあり、取り返しがつかないことになりかねません。
また、アドバイスを受けることで見通しが立ち、安心して治療に専念できるという効果もあります。
3 適切な等級認定に向けた資料収集を期待できる
弁護士に申請手続を依頼しない場合、通常、任意保険会社が申請手続を行います。
しかし、任意保険会社に申請手続を任せた場合、被害者のために、積極的に有利な資料を収集してくれるとは限りません。
等級認定の審査は原則として書面審査であるため、被害者が対面で症状を訴えることはできず、症状を裏付ける資料を収集・提出しなければなりません。
弁護士に依頼した場合には、弁護士は、適切な等級認定に向けて積極的に資料を収集することが期待できます。
4 不服申し立て手段・訴訟
後遺障害の等級認定結果に不服がある場合、異議申立手続、自賠責保険・共済紛争処理機構に対する申立てなどの不服申立手段や、訴訟提起して裁判官に等級認定についての判断を仰ぐといった方法があります。
これらの手続きは複雑かつ専門的知見が必要であるため、被害者本人で対応することは容易ではありません。
弁護士に依頼した場合であれば、採るべき手段の選択や見通しについてアドバイスを受けることができますし、その手続についてもお任せすることができます。
5 当法人にご連絡ください
当法人では、後遺障害チームを作り、適切な等級認定の獲得できるよう全力でサポートしております。
後遺障害について些細なことで気になることがあれば、お気軽に弁護士法人心 岐阜法律事務所までご連絡ください。
後遺障害について依頼する際の弁護士費用
1 後遺障害について弁護士にする場合の費用

適切な後遺障害の等級を獲得するには、保険会社にお任せにするのでなく、弁護士に申請手続を依頼すべきです。
では、後遺障害について弁護士に依頼する場合の費用はどの程度かかるのでしょうか。
以下、当法人における弁護士費用の目安をご紹介いたします。
2 簡易な後遺障害申請の場合
申請書類の作成のみをサポートする場合を指します。
この場合、着手金は無料、報酬金は下表のとおり獲得等級に応じたものになります。
| 獲得等級 | 報酬金 |
|---|---|
| 14級 | 3万3,000円 |
| 13級 | 5万5,000円 |
| 12級 | 8万8,000円 |
| 11級 | 9万9,000円 |
| 10級 | 13万2,000円 |
| 9級 | 17万6,000円 |
| 8級 | 23万1,000円 |
| 7級 | 24万2,000円 |
| 6級 | 28万6,000円 |
| 1~5級 | 獲得金額の2.2% |
3 簡易な後遺障害申請でない場合
診断書や検査内容の検証等を含めたサポートを行う場合、簡易な後遺障害申請と比較して、事案の難易度や労力の程度が異なります。
そのため、事案の難易度やサポート内容等に応じて、2の金額の2~4倍程度を弁護士費用の目安としています。
4 異議申立てを行い、新たに等級認定を獲得した場合、又は昇級した場合
異議申立てをして新たに等級認定を獲得した場合や、昇級することは、一般的に難易度が高いため、上記2や3の金額の1.5倍程度を報酬金の目安とします。
5 弁護士費用特約が利用できる場合
自動車保険等に弁護士費用特約が付いている場合、これをご利用いただくことで、保険会社から各保険会社の規定の範囲で弁護士費用や実費が支払われます。
後遺障害についての弁護士費用も対象となります。
弁護士費用特約を利用することで、依頼者様のご負担が少なくなる、あるいは、なくなりますので、事故に遭われた際には必ず弁護士費用特約が付いているか確認しましょう。
6 当法人にご連絡ください
相談者様の事案において弁護士費用がどの程度かかかるかは、事案の内容をお聞かせいただければ、弁護士からご説明いたします。
当法人では、交通事故の相談費用はもちろん、後遺障害適正等級診断サービスを無料でご用意しておりますので、後遺障害について些細なことで気になることがあれば、お気軽に弁護士法人心 岐阜法律事務所までご連絡ください。
後遺障害等級認定について
1 交通事故における後遺障害

交通事故で負った怪我を治療しても症状の改善が見られず、後遺症が残ることがあります。
後遺症について後遺障害等級認定を受けると、「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」などの後遺障害の損害についても補償を受けることができるようになります。
2 後遺障害等級認定を獲得するメリット・デメリット
⑴ メリットは、前述のとおり、後遺障害の損害についても補償を受けられるようになることです。
「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」のほかにも、後遺障害の内容や程度に応じて、「将来介護費」や「家屋改造費」などもあります。
いずれも高額になることが多く、後遺障害の等級認定を得るメリットは大きいです。
⑵ デメリットについては、とくにありません。
あえていえば、申請書類の取り付け費用の負担があったり、申請から認定結果が出るまでに一定期間要することが考えられます。
3 後遺障害等級認定の申請手続
治療しても症状の改善が見込まれない状態(「症状固定」といいます。)になると申請手続を進めます。
後遺障害診断書などを医師に作成してもらい、その他必要書類と一緒に自賠責保険会社に提出します。
申請方法には、保険会社が申請する「事前認定手続」と、被害者が申請する「被害者請求手続」がありますが、原則として、「被害者請求手続」の方法によるべきです。
保険会社は加害者側の立場であるため、被害者の等級認定に向けて最善を尽くすとは限らないからです。
被害者請求手続による場合、事前認定手続きと比べて資料収集の手間がかかりますが、弁護士に依頼すれば、被害者の手間を最小限にとどめることができます。
4 後遺障害等級の内容
障害の内容や程度に応じて1級から14級まで用意されています。
自動車損害賠償保障法施行令の別表第1、第2に後遺障害別等級表があり、等級ごとの後遺障害の内容を一覧することができます。
別表第1は、介護を要件とするものであり、その程度により1級と2級があります。
別表第2は、介護を要件としないものであり、1級から14級まであります。
後遺障害と聞くと、手足の切断がなければ認定されないのではないかとお考えの方もいますが、むち打ち症でも、12級や14級の認定がされることがありますので、等級認定の可能性があるか弁護士にご相談されることをお勧めします。
5 適切な等級認定を得るために弁護士にお早めにご相談ください
後遺障害等級認定は、等級認定基準に基づき判断されます。
認定基準について正確な理解がないと、十分な資料収集ができず、適切な等級認定を獲得することができません。
適切な等級認定を獲得するためには、早めに弁護士に相談して申請準備に備えていくことが大切です。
当法人には交通事故チームがあり、多くの等級認定を獲得してきた実績があります。
ご自身・ご家族の事故で後遺障害が問題となるのか、どのような等級認定がありうるかなど、些細なことでも気になることがございましたら、お気軽に、弁護士法人心 岐阜法律事務所にご連絡ください。
下肢の欠損障害について
1 下肢の欠損障害における等級

交通事故によって下肢を欠損した場合、どの部分から欠損しているかによって、後遺障害の等級認定は次のとおり定められています。
⑴ 第1級5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
⑵ 第2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの
⑶ 第4級5号 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
⑷ 第4級7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
⑸ 第5級5号 1下肢を足関節以上で失ったもの
⑹ 第7級8号 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
2 等級の内容について
⑴ 「下肢をひざ関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
ア 股関節において寛骨(骨盤を構成する左右一対の骨)と大腿骨を離断したもの
イ 股関節とひざ関節との間において切断したもの
ウ ひざ関節において、大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断したもの
⑵ 「下肢を足関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
ア ひざ関節と足関節との間において切断したもの
イ 足関節において、脛骨(ひざから足首の間にあり、脚の内側前面にある骨)および腓骨(ひざから足首の間にあり、脚の外側にある骨)と距骨(足首付近にある骨)とを離断したもの
⑶ 「リスフラン関節(指の骨と立方骨、甲の骨を繋ぐアーチ状の構造をした関節)以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
ア 足根骨において切断したもの
イ リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断したもの
3 損害賠償請求の注意点
下肢の欠損は今後の生活において重大な支障を来たすので、ご自身・ご家族のためにも、相手方に損害賠償を請求するときには、将来において発生する損害についても、しっかりと考えなければなりません。
⑴ 逸失利益
下肢の欠損により、将来において収入が大幅に減額するおそれがあるため、労働能力が低下したことによる逸失利益の補償を十分に受ける必要があります。
⑵ 装具・器具の費用
下肢を支えるために義足を製作したら、必要かつ相当な範囲でその費用を相手方に請求することができます。
また、装具は変わりなく使えるものではなく、将来的に買い替えも予定されます。
したがって、相手方に賠償を求めるときは、平均余命までの交換回数を計算したうえで請求する必要があります。
義足に限らず、車椅子等も同じように考えることができます。
⑶ 家屋・自動車等改造費
下肢を失ったことにより、義足や車椅子での生活になると、家屋を障害に合わせてバリアフリー化する必要性も生じます。
自動車に手動運転補助装置をつけたり、自動運転車に買い替えたりする可能性もあるため、必要かつ相当な範囲でその費用を相手方に請求することができます。
⑷ 将来介護費用
下肢欠損は、自賠責後遺障害の別表1第1の1級や2級といった要介護の後遺障害等級ではありません。
しかしながら、下肢の欠損によって歩行、昇降するのに、人の助けを必要とする可能性もあります。
したがって、事案に応じて、相手方に将来介護費の支払いを求めていく必要があります。
4 示談をする前に弁護士に相談を
今回ご紹介した費用以外にも被害者の状況によっては、将来の損害を請求できる場合があります。
しかし、示談をしてしまうと、二度と請求が出来なくなってしまうので、示談をする前に、一度、弁護士への相談をおすすめいたします。
交通事故と鎖骨変形の後遺障害
1 交通事故による鎖骨骨折

交通事故で自転車やバイクから転倒したりすると、肩や腕に衝撃が加わり、鎖骨を骨折することがあります。
鎖骨を骨折すると、身体中央に近い方は胸鎖乳突筋によって上に引っ張られ、肩側の方とずれが生じます。
これはレントゲン検査により確認できます。
その後の治療経過によって、鎖骨の変形障害、肩関節の可動域制限などの後遺障害が残ることがあります。
ここでは、鎖骨骨折による後遺障害のうち、変形障害についてお話します。
まず、鎖骨骨折の場合、保存療法が期待できる場合には、整復により骨を正しい位置に戻して鎖骨バンドなどで固定します。
他方、骨折によるずれの程度が大きい場合などでは手術の方法を選択することもあり、この場合、プレートやワイヤーを用いて固定したりします。
整復による場合、その症状の程度によっては、ずれた状態で癒合することもありますが、手術による場合には骨折部がずれることなく、後遺障害が残ることは少ないと考えられています。
3 後遺障害
骨の変形障害については、自賠責の後遺障害等級表にて12級5号に、「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」とあります。
ここでいう「著しい変形」とは、裸体となったとき、変形が明らかにわかる程度のものをいいます。
したがって、鎖骨変形の後遺障害があるか否かは、鏡の前で裸になって変形が明らかに分かるかどうかという点が、判断の指標となります。
4 鎖骨変形と逸失利益
鎖骨変形で後遺障害等級12級5号の認定がなされた場合、保険会社との間で、後遺障害逸失利益について争いになることが少なくありません。
保険会社の主張は、鎖骨変形によっても労働能力への影響はない又は限定的だろうというものです。
この点、容姿が重視される仕事(モデルなど)では労働能力に大きな影響を及ぼすことが考えられるので、逸失利益は認められやすいといえます。
同様に、鎖骨変形に加えて、それを原因とする疼痛等がある場合には、将来的に業務への支障が考えられるため、逸失利益が認められることもあります。
裁判例でも、積載車の運転手が、鎖骨変形で後遺障害等級12級5号の認定等がなされた事案において、右肩の痛みや、現実に減収したことなどを踏まえて、逸失利益を認めたものがあります。
このように、鎖骨変形の事案では、必ずしも逸失利益が否定されるとは限らず、被害者の症状の内容や程度、業務内容、業務への支障などを踏まえ、個別的に判断されるべきであるといえます。
5 弁護士に相談
このように、鎖骨変形の事案では、適切な後遺障害等級を獲得することはもちろん、その後の賠償交渉で適切な賠償額を獲得するためには、しっかりと準備して臨む必要がありますので、弁護士へのご相談をお勧めします。
鎖骨骨折のお怪我を負った場合には、お気軽に弁護士法人心 岐阜法律事務所までご連絡ください。
後遺障害と装具費用
1 装具費用について

交通事故で後遺障害が残った場合に、生活を補助するために、義足、車椅子などの装具の購入が必要になることがあります。
これら装具費用については、必要かつ相当なものであれば、損害として認められます。
また、装具は時間の経過により消耗するため、相当期間で買い替えなければなりません。
この将来の買い替え費用についても、必要かつ相当な範囲で認められますが、後述のとおり中間利息を控除しなければなりません。
事案によっては、多数回の買い替えが必要となり、その金額も多額になったりしますので、請求漏れのないようにしっかりと確認しましょう。
2 中間利息の控除について
本来は、将来買い替えが必要になったときに買い替え費用が具体的に発生します。
しかし、実務では、将来に発生するだろう買い替え費用も含めて一時金で賠償する方法が多く採られています。
この場合、被害者は、一時金として受領した賠償金を銀行に預けるなどして運用すれば利息分の利益を得られることになってしまいます。
そのため、将来の装具費用の算出では、この中間利息を控除する必要があります。
分かりにくい問題ではありますが、例えば、平均余命22年、100万円の車椅子(耐用年数6年で3回買い替え必要)とした場合で考えてみます。
この場合に症状固定時に1台目を購入すると仮定したときの費用は、次のように計算します。
100万円×(1+0.8374+0.7013+0.5873)=312万6000円
3 必要性、相当性の立証資料について
装具費用の必要性、相当性については、医師の意見書、装具のカタログ、被害者の生活状況に関する報告書等から、当該装具が必要な状態であること、金額も相当額であることなどを立証することになります。
4 注意点
義足や車椅子が必要な場合、例えば、身体障害者として一定の公的扶助(補装具費の支給など)を受けられることがあります。
支給済みであったり、支給が確定している場合には、損益相殺として賠償額から控除しなければなりませんが、いまだ支給分が確定していない将来分については、賠償額から控除されません。
賠償額の算定の際には注意が必要です。
5 弁護士法人心にご相談ください
装具費用については必要性、相当性などで争われることが少なくなく、十分な証拠資料を収集しておく必要があります。
装具費用その他損害賠償についてお困りの場合には、お気軽に弁護士法人心 岐阜法律事務所までご連絡ください。
高次脳機能障害と後遺障害
1 高次脳機能障害とは

高次脳機能障害とは,脳を損傷することで,意思疎通能力,問題解決能力,作業負荷に対する持続力・持久力,社会行動能力に支障が生じることをいいます。
例えば,メモしておかなければ簡単なことでも覚えていられなかったり,何度も同じ間違いをおこしてしまったり,優先順位をつけた計画が立てられない,対応が以前より子供っぽくなるといったことがあげられます。
これら症状は,損傷を受けて2年,3年と経つにつれ,回復は鈍りはじめていくといわれています。
したがって,早期に傷病を特定し,治療を進めていくことが大切です。
2 高次脳機能障害と後遺障害
交通事故でも脳を損傷して高次脳機能障害の診断を受けることがあります。
治療を受けても,残念ながら上記のような症状が残ってしまった場合には,後遺障害等級認定の申請を行うことになります。
自賠責保険は,高次脳機能障害の等級について,基本的に,1級~3級,5級,7級,9級を想定しています(参考リンク:後遺障害等級表)。
等級判断においては,外傷性の脳損傷があるか否か,これが認められたとして,意思疎通能力,問題解決能力,作業負荷に対する持続力・持久力,社会行動能力の4つの能力がどの程度失われたかといった点に着目して審査されます。
3 後遺障害申請における注意点
⑴ 画像検査
外傷性の脳損傷であることについては,画像所見や事故直後の意識障害の存在等を踏まえて判断します。
画像所見については,MRI検査やCT検査の結果から立証することになるため,事故後しっかりと検査を行っておくことが重要となります。
また,MRIには3.0テスラ,1.5テスラなどありますので,可能であれば,より解像度の高いMRIで検査を受けることが望ましいといえます。
⑵ 意識障害
重度の意識障害が相当期間継続すると,脳に何らかの損傷が発生したと推認させる事情になります。
意識障害の程度や時間については救急搬送先の医療機関から診断書やカルテを取り付けることで確認することができることが多いですが,明らかでない場合には,救急出動報告書等を取り付ける必要もあります。
⑶ 行動変化の記録
次に,事故前後における被害者の変化も重要なポイントであるといえます。
これは,4つの能力がどの程度失われたか判断する際の参考にされます。
後遺障害申請書類に,日常生活の変化を報告する「日常生活報告書」という必須の書類があり,これは,被害者の様子をよく観察しているご家族等身近な方に作成いただきます。
正確に報告書を作成できるよう,被害者の症状や言動などを事細かくメモして残しておくことをお勧めします。
入院中は医師や看護師が被害者の対応をしていますが,ずっと付き添っているわけではありませんので,ご家族等の方で積極的に観察し記録を残しておくようにしましょう。
4 弁護士にご相談ください
これまで申し上げたものを含め,高次脳機能障害では,受傷初期から注意して取り組まなければならないことがたくさんあります。
ご家族など周りの方で,脳挫傷,びまん性軸索損傷などの診断がなされたり,医師から高次脳機能障害のお話がなされた場合には,まずは,弁護士にご相談ください。
適切な後遺障害の賠償を得るために大切なこと
1 適切な等級認定を獲得することが大切

後遺障害の等級認定がなされると、後遺障害の損害についても賠償を受けることができるようになります。
後遺障害の損害としては、「後遺障害慰謝料」、「逸失利益」及び「将来介護費」などがあります。
これらは、後遺障害等級認定の内容・程度に応じて、その賠償額が大きく異なります。
また、将来介護費等は重度の後遺障害等級を獲得できなければ全く認められないこともあります。
したがって、適切な後遺障害の賠償を得るためには、症状に応じた適切な等級認定を獲得することがなによりも大切です。
2 通院の継続が重要
治療継続しても症状改善に向けた治療効果が見込まれない状態(これを「症状固定」といいます。)に至ると、後遺障害申請手続を進めます。
仮に、症状改善が見込まれるにもかかわらず、後遺障害申請手続を進めようとすると、将来においても回復が困難なものではないとして、後遺障害認定上、不利に考慮されてしまう可能性があります。
また、通院を継続していても、忙しくてほとんど通院できていなければ、残った症状と受傷当初の症状が一貫しているか明らかでないとして、不利に考慮される可能性もあります。
したがって、症状がある間は症状の改善に向けてしっかり通院継続し、治療効果が見込まれない状態である症状固定の状態に至ってから後遺障害申請手続を進めるようにしましょう。
3 等級認定において必要な検査を受けておくこと
後遺障害の等級認定では、必要な検査を受けていないと不利に考慮される場合があります。
例えば、動揺関節が問題となる場合には、ストレスXPテストを受けておく必要がありますし、耳鳴りが問題となる場合には、ピッチ・マッチ検査とラウドネス・バランス検査を受けておくことが必要です。
保険会社や医師は、後遺障害等級認定でどのような検査が必要となるか、必ずしも教えてくれないため、早めに弁護士に相談しておくことをお勧めします。
4 医師に誤解されないこと
後遺障害の申請では、主治医が作成する後遺障害診断書を提出します。
後遺障害診断書には、症状固定時の症状が記載されます。
したがって、適切な等級を獲得するには、後遺障害診断書に症状の内容等が適切に反映されていなければなりません。
そのため、症状を伝える際には医師に誤解されないよう注意しましょう。
また、作成された後遺障害診断書の内容は必ずチェックし、仮に、症状が適切に反映されていない場合には、医師に対して追記や修正の依頼をしましょう。
5 被害者請求
後遺障害申請手続には、任意保険会社にお任せする事前認定と、被害者側で行う被害者請求の2つがあります。
任意保険会社は、あくまで加害者側の立場であるため、等級認定に向けて最善を尽くしてくるとは限りません。
適切な等級認定を獲得するためには、被害者請求の方法で申請するようにしましょう。
6 弁護士法人心にご相談ください
適切な等級認定を獲得するには、通院における注意点、必要な画像検査などの知識をできるかぎり早めに知っておく必要があります。
また、後遺障害診断書のポイントなどは交通事故に精通した弁護士でないと適切なアドバイスができません。
当法人では、交通事故を集中的に取り扱う弁護士や損害料率算出機構で長年勤務したスタッフらで構成する交通事故チームで対応しており、適切な等級に認定に向けて日々取り組んでおります。
適切な後遺障害の賠償を獲得されたいとお考えの場合には、弁護士法人心 岐阜法律事務所までお気軽にご連絡ください。
後遺障害と家屋改造費
1 家屋改造費について

交通事故によって、身体に麻痺が残り、車椅子による移動を余儀なくされたり、関節の動きが制限され、段差の昇降などが困難になったりした際には、スムーズに日常生活を送れるよう、ホームエレベーターの設置や段差解消、手すり等の設置など、家屋を改造する必要がでてくることがあります。
このような改造や設置費用は、被害者の受傷の内容、後遺障害の内容・程度から必要と認められれば、「家屋改造費」という損害として、相当額が支払われます。
重度の後遺障害等級を認定された方であれば必要性が認められやすいといえますが、そうでなくとも、改造する必要があることを立証できれば、賠償金として支払われる可能性もありますので、請求漏れがないよう、何を請求できるかしっかり検討する必要があります。
2 家屋改造費を請求するには
家屋改造費を請求する際には、少なくとも、改造にかかった費用が分かる資料(工事会社の見積書や明細書、領収証)と、どこの部分を改造したのかが分かる資料(改造前と後の図面や写真)が必要になります。
事案によっては、被害者と同居している家族が、被害者の日常生活について報告書を作成したり、医師に改造後の仕様が必要であることの意見書を作成してもらうなど、より細かな証明が必要となることがあります。
3 注意すべき点
家屋を改造することで、一緒に住む家族もその利便性を共有するような場合や、あまりにも高級な仕様であったりする時には、その部分の損害が認められず、減額されることもあります。
改造する際には、工事会社からの見積もりを十分に確認し、合理性を欠くような華美な装備がなされていないか等をチェックすることも重要です。
4 弁護士にご相談ください。
前述のとおり、家屋改造費では、改造が必要であり、費用が相当であることが求められるので、立証資料を揃えておく必要があります。
家屋の改造を予定されている方や、改造したものの相手方に請求できるか分からないとお悩みの場合には、まずは弁護法人心の弁護士にご相談ください。
経験豊富な弁護士・スタッフが誠心誠意対応させていただきます。